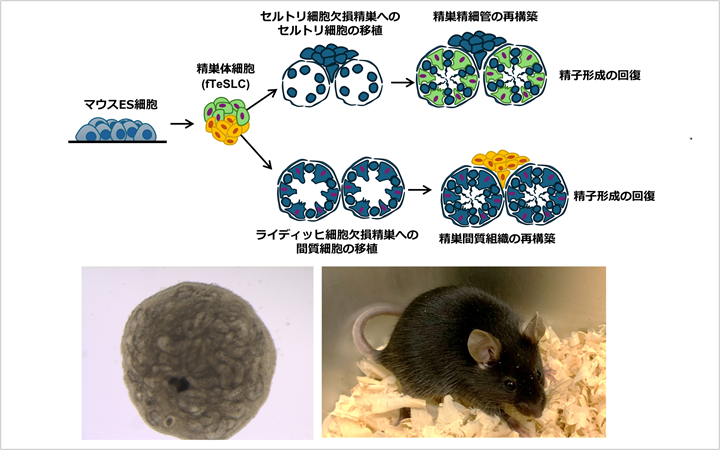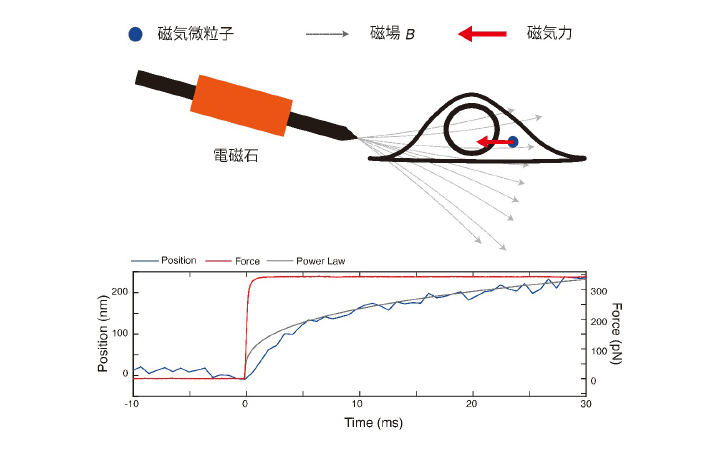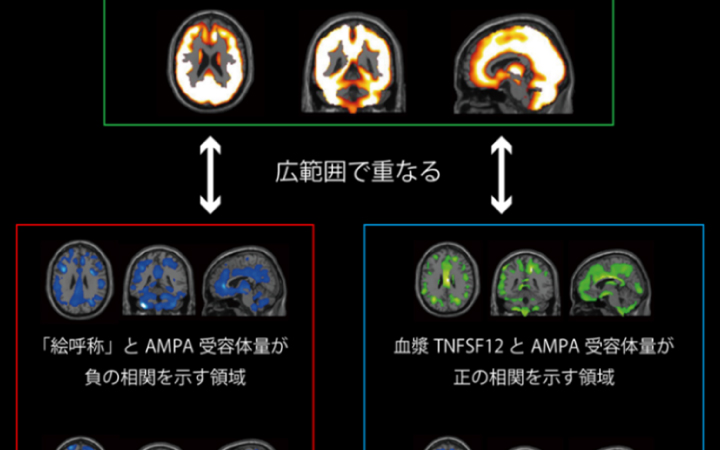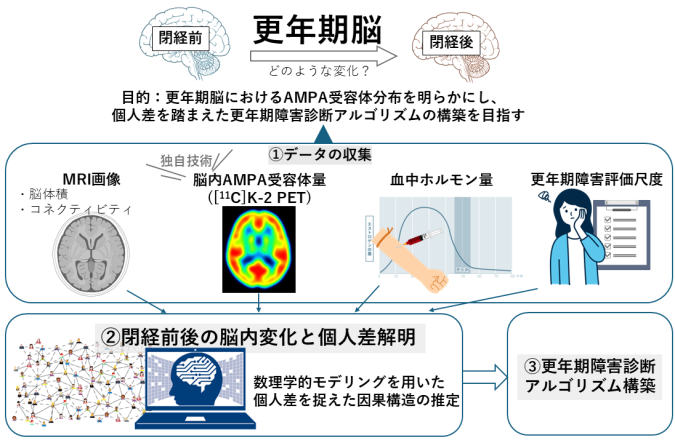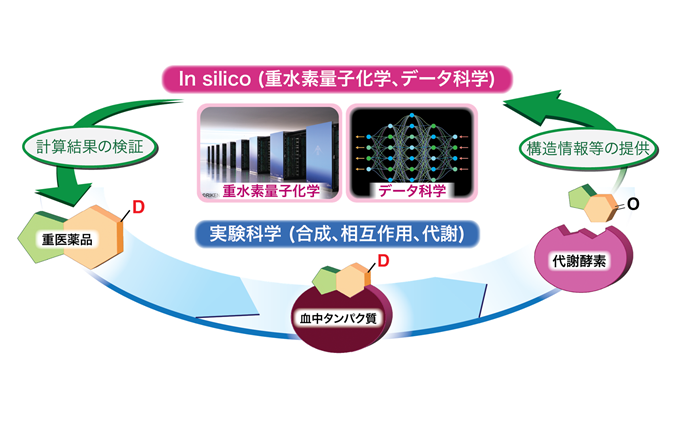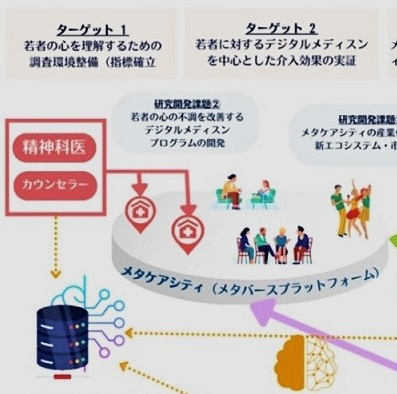ニュース&トピックス
YCUの研究最前線
注目の研究者
-
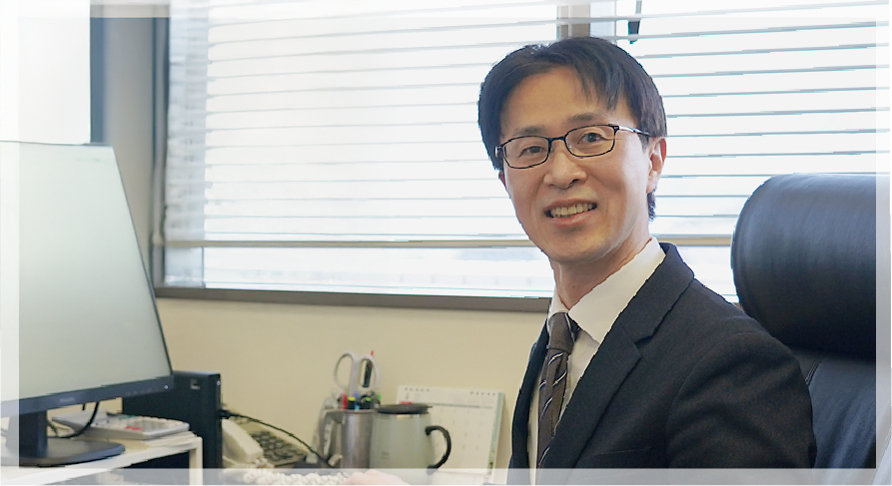
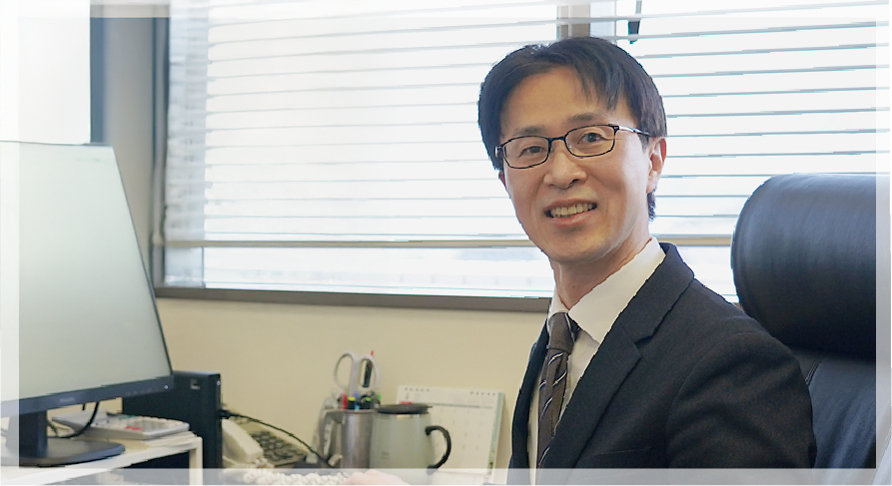
免疫学および微生物学の未解決課題に挑み、難治性炎症疾患や感染症治療への応用を目指す
医学研究科 微生物学 教授 浅野 謙一
「免疫細胞が炎症や病気の回復にどう関わるのか?」ということをテーマに研究をしています。例えば、細菌やウイルスなどの微生物が体に入ると、免疫細胞はそれを排除しようとします。でも、攻撃しすぎると今度は自分の体を傷つけてしまうことがあります。特に、感染症や慢性炎症では、免疫細胞の働きが病態を左右するため、うまくバランスを取ることが大切です。ここでポイントになるのが、「微生物と免疫の関係」を知ること。細菌やウイルスが体の中に侵入するとき、免疫細胞はそれを排除しつつも、自らの働きを適切に制御しなければなりません。微生物の戦略を知ることで、免疫の応答をより深く理解でき、新たな治療法の糸口が見えてきます。私は、免疫細胞が過剰な応答を抑え、炎症で傷ついた組織を再生する仕組みを理解することで、自己免疫疾患や炎症性疾患、難治性の慢性感染症などの治療法開発に挑戦しています。 -


観光という現象を地理学の視点から分析し捉えようとする学問、観光地理学の研究
都市社会文化研究科 都市社会文化専攻准教授 有馬 貴之
研究の調査の一つとして空間分析、つまりGIS(地理情報システム)を用いた人の流れの解析があります。どこにいた人が、どんな動機を持って、どんな手段で、どこに移動しているのか、そこで何をするのか、といった情報は、地域の魅力を客観的に理解し、かつ観光地や地域、商業施設など、あらゆる空間の活用のためのヒントになります。
活用といっても、来場者数が多ければ多いほど良いというわけではありません。オーバーツーリズムといって観光客が増えすぎることで地域住民の生活や自然環境に悪影響を及ぼし、問題になった観光地も多くあります。いずれにせよ、観光客の行動を分析し、理解することができると、それはさまざまなことに応用できます。 -
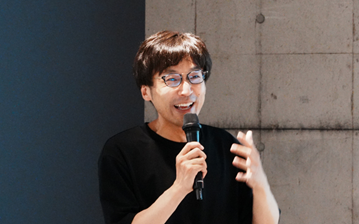
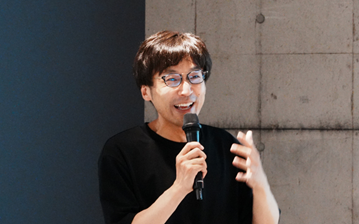
「ことばの交換」の実用化を目指して、本学初となる人文学・社会科学分野の大学発認定ベンチャーの(株)STUDIUSを設立
国際マネジメント研究科 准教授 伊藤 智明 株式会社STUDIUS 代表取締役
大学院で経営学のあり方を模索する中で、ひとりの起業家と出会ったことをきっかけにして、2011年4月21日に「ことばの交換」の開発に着手しました。「ことばの交換」では、ふたりの参加者がよく分からないことに対峙する経験を積み重ねていくこと、積み重ねた経験から分かったことを自分のことばとして話してみること、自分のことばで話そうとしている相手の声を聞こうとすることを大切にしてきました。ふたりで13年続けることができた「ことばの交換」の実用化を目指して、2024年4月23日に株式会社STUDIUSをふたりで設立しました。当社のミッションは「わたしたちが安心して夢中になれる」時空間を提供することです。 -


経営学やマーケティングを医療・健康・介護に応用する「医療経営」研究
国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 准教授 原 広司
「医療経営」は、患者さんのニーズや医療資源、職員満足度など医療を取り巻く諸要素をマーケティングや経営学を用いて調査し、より良い医療につなげていくために研究する学問です。こどもから高齢者まですべての人の健康をターゲットにしており、たとえば高齢者を対象とした研究では、介護施設と医療機関の連携状況を調査し、密な連携がより良いサービスにつながっていることを明らかにしました。
注目の研究
YCUの研究マップ


産学官連携/産学官連携をお考えの皆様へ