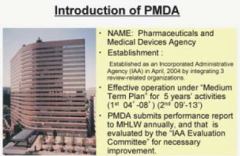
医薬品医療機器総合機構(PMDA)との連携
2008年、PMDA理事長に初めて臨床医が就任することとなり、新薬や医療機器審査の視点が変わってきました。科学(レギュラトリーサイエンス)を優先しながら、かつ臨床医の現場感覚や、必要度・緊急度などを薬事行政に取り入れ始めたのです。このような背景の元で、PMDAは臨床専門医の豊富な知識と経験が審査に必要となり、大学との連携を求めていました。一方、本学は基礎研究を実用化に活かすトランスレーショナルリサーチ(橋渡し研究)を強化するため、臨床研究・治験の解る臨床医の育成を目指していました。そこで両者の思いが重なり、2010年4月、全国に先駆けて連携大学院を発足させました。今後、医学研究の新しい分野として、本連携大学院を大きく発展させていきます。

理化学研究所との連携
2008年度より、理化学研究所ゲノム医科学研究センターとの連携大学院をスタートしました。骨関節疾患、アレルギー性疾患、内分泌・代謝性疾患、脳疾患、腫瘍性疾患、循環器疾患等に関わる遺伝性因子の探索、全ゲノム遺伝統計解析法、ファーマコゲノミクスなど数々の最先端の研究を理化学研究所で行い、横浜市立大学で学位を取得するプログラムです。

放射線医学総合研究所との連携

横浜国立大学との医工連携
医学研究科では、2008年度より、文部科学省グローバルCOEプログラム「情報通信による医工融合イノベーション創生」に取り組んでいます(拠点校:横浜国立大学、連携機関:オウル大学(フィンランド)・情報通信研究機構)。本取組は、世界最高水準の医工融合研究を行う科学者・エンジニア・医師の育成、また、医学博士と工学博士の2つの学位取得を可能にするダブル・ディグリー制度の確立を目標としています。

国立感染症研究所との連携
国立感染症研究所は、感染症を制圧し、国民の健康医療の向上を図る予防医学の立場から、広く感染症に関する研究を先導的・独創的かつ総合的に行い、国の保健医療行政の科学的根拠を明らかにし、また、これを支援することを目的としています。医学研究科と国立感染症研究所は、相互に連携を行うことで、感染症に関する教育研究活動の推進及び医療活動の充実を図り、もって医療及び学術の発展に寄与するために、協定を締結しました。国立感染症研究所の研究者を医学研究科の客員教員として迎え、共同で研究指導、講義を行っていきます。

神奈川県立こども医療センターとの連携
医学研究科では、大学院生を小児医療の現場に即した高度な研究環境で研究を行え、こども医療センターの医師、研究者を医学研究科の客員教員として迎え、共同で研究指導、講義を行うことなど、双方が連携することにより活発な人的交流、人材育成、情報交流等を行っていきます。


神奈川県立がんセンター臨床研究所との連携
神奈川県立がんセンター臨床研究所(以下、臨床研究所)は、がん分子病態学、がん生物学、がん治療学、がん予防・情報学の4つの部からなり、その下部に7つのプロジェクトチームを擁しています。臨床研究所では、それらの組織が有機的な連携を保ちながら、がんの基礎医学的研究から、その成果が癌の診断・治療に直結するトランスレーショナルリサーチ、がんの疫学まで幅広い研究分野に展開しています。医学研究科では、臨床研究所の研究者を客員教員として迎え、腫瘍病理学の分野において、共同で研究指導、講義を行うとともに、臨床研究所に大学院生を派遣しての研究活動など、交流等を図っていきます。
国立国際医療研究センターとの連携

公益財団法人がん研究会との連携
公益財団法人がん研究会は、1908年に創立された日本で最も古いがん研究機関です。2005年からは、豊島区上池袋から江東区有明に移転し、併設されているがん専門病院のがん研有明病院との連携のもとで、基礎研究から橋渡し研究、臨床研究に至るまで、日本のがん研究の発展に大きな貢献を果たしています。
医学研究科とがん研究会は、がんの基礎研究・臨床研究の分野における将来のリーダーとなる人材育成を視野に入れ、連携を進めていきます。国立成育医療研究センターとの連携
横浜市立市民病院との連携
横浜市立脳卒中・神経脊椎センターとの連携
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターとの連携
日本の厚生労働省所管の国立研究開発法人で、国立高度専門医療研究センター(ナショナルセンター)です。
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人であり、精神疾患、神経疾患、
筋疾患及び知的障害その他の発達の障害に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び
技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことができる国内有数の機関です。
2018年4月、連携大学院協定を締結し、教育・研究活動のさらなる連携を進めていきます。


