選手との触れ合いとボランティア同士の交流。学内では得られない体験を!
■日時:
5月17日(土)/エリートパラ、エリート
18日(日)/エイジグループ(パラ、スタンダード、スプリント、リレー)
■場所:横浜市山下公園周辺特設会場(山下公園スタート・フィニッシュ)
■主催団体:世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
■ボランティア学生数:17日/2名、18日/2名
■イベントの規模:参加選手/エリートパラ・エリート155名、エイジグループ1,505名
観客/2日間約270,000名、スタッフ/約2,650名、ボランティア/約1,950名、本学ボランティア/延べ4名
5月17日(土)/エリートパラ、エリート
18日(日)/エイジグループ(パラ、スタンダード、スプリント、リレー)
■場所:横浜市山下公園周辺特設会場(山下公園スタート・フィニッシュ)
■主催団体:世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
■ボランティア学生数:17日/2名、18日/2名
■イベントの規模:参加選手/エリートパラ・エリート155名、エイジグループ1,505名
観客/2日間約270,000名、スタッフ/約2,650名、ボランティア/約1,950名、本学ボランティア/延べ4名

■大雨の大会となった初日の「エリート」
5月17日(土)18日(日)の2日間、山下公園を中心に「2025ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会」が開催され、本学から延べ4名の学生ボランティアが参加し、取材に行った初日のエリート(世界を転戦しながらポイントを獲得し、年間のチャンピオンを決定するシリーズ戦)には、2名の学生が参加しました。
今回で記念すべき15回目の開催となった本大会ですが、一日を通してあいにくの大雨となり、本来の力を出し切れず悔しい思いをした選手も多かったようです。しかしそんなコンディションの中でも、ボランティアの学生たちはフィニッシュした選手に向けて、積極的な声掛けなど温かいホスピタリティで対応していました。
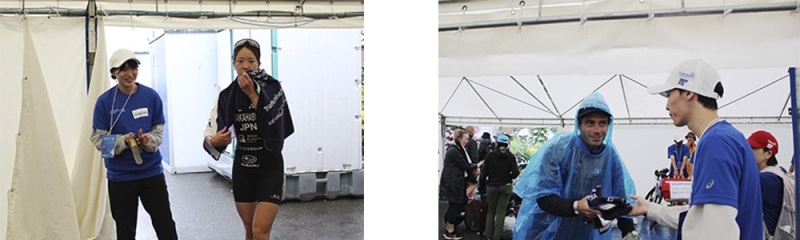
■汗と涙と、滴る雨
初日に活動した学生は主に「エリート女子」のレース担当として、大雨に見舞われコンディションが悪い中戦いを終えて戻ってきた選手のサポートを行いました。この活動は英語を使う機会も多いため本学では毎年人気です。今回は締め切りが春休み中と早かったこともあり、例年に比べてボランティアの参加者が少なかったのですが、その分一人当たりの活動量が多くなったので、大変ではありましたが逆に充実した活動となったようです。
学生ボランティアは、 計測チップを外し(女子選手なので女子が対応)、ドリンクやタオルを渡すなど英語を使った労いのことば掛けをして、選手の皆さんから「ありがとう」と返してもらっていました。現場には大会のキッズプログラムで参加した市内の小学生ボランティアもいて、我先にという元気さで周囲を笑顔にしていましたが、英語の対応は大学生が担いました。学生ボランティアが胸につけた「English」の文字を見て、選手だけでなくメディアや計測員の方が話しかけてくることもあり、そんな場合にも堂々と対応していました。
学生ボランティアは、 計測チップを外し(女子選手なので女子が対応)、ドリンクやタオルを渡すなど英語を使った労いのことば掛けをして、選手の皆さんから「ありがとう」と返してもらっていました。現場には大会のキッズプログラムで参加した市内の小学生ボランティアもいて、我先にという元気さで周囲を笑顔にしていましたが、英語の対応は大学生が担いました。学生ボランティアが胸につけた「English」の文字を見て、選手だけでなくメディアや計測員の方が話しかけてくることもあり、そんな場合にも堂々と対応していました。

■参加したボランティア同士の交流
選手がスタートしてからフィニッシュしてくるまで2時間弱の空き時間では、一緒にボランティアとして参加していたさまざまな企業の方との交流もできました。お互いボランティア参加についての共通の思いを話し合い、現役社会人の方からは仕事や採用の話、企業が若い人に期待することなど、大学生としてたいへん有意義なお話を聞くことができたようです。
このようにボランティア活動は、普段キャンパス内にいるだけでは経験できないさまざまな立場の違う方との交流を通して、学生が成長する現場です。今回はスポーツイベントが対象でしたが、そのほかにも国際会議や学習支援、障害児者支援、環境保全活動等のさまざまな活動の場を紹介しています。
このようにボランティア活動は、普段キャンパス内にいるだけでは経験できないさまざまな立場の違う方との交流を通して、学生が成長する現場です。今回はスポーツイベントが対象でしたが、そのほかにも国際会議や学習支援、障害児者支援、環境保全活動等のさまざまな活動の場を紹介しています。

■18日の「エイジグループ」では短時間の間に約1,500名に対応
天候も回復した翌18日(日)の「エイジグループ」では、パラトライアスロン、スタンダード、スプリント、リレーの各カテゴリーに、高校生から80代のご高齢の方まで合計約1,500名の一般選手が参加し、各々の目標である完走やタイム更新に挑戦しました。
2日目の本学のボランティア2名は、それぞれスタート前のエイドと、選手受付を担当しました。活動時間は4時間半と短かったのですが、選手はカテゴリー毎・年齢毎に順次受け付けしてスタートに流れていくので、ボランティアもその間は休みなく約1,500名の選手対応を行う必要があり、集中力も必要な活動でもありました。
2日目の本学のボランティア2名は、それぞれスタート前のエイドと、選手受付を担当しました。活動時間は4時間半と短かったのですが、選手はカテゴリー毎・年齢毎に順次受け付けしてスタートに流れていくので、ボランティアもその間は休みなく約1,500名の選手対応を行う必要があり、集中力も必要な活動でもありました。
■学生のコメント
○今回の活動で最も印象的だったことは、大手企業に勤めている会社員の方と交流できたことです。大学で学んだことは社会に出てからはどのように活かされることがあるのか、「ボランティア活動も含め大学時代で自発的に活動したことの大切さを踏まえて、仕事に就いてからも学ぶことはたくさんあるから、自分に合う雰囲気の会社を探せるといい」といったアドバイスをもらえました。また、活動場所のリーダーさんは横浜市役所で働いている方で、公務員がどんなことをしているのか、決して変化に乏しい仕事ではないことを知ることができました。大学内では会えないような方と交流できるのがボランティアの魅力だなと改めて思いました。
○選手との関わりを通して感じたことは、世界規模の場ではやはり英語が話せるというだけで周りからの扱いが変わるということです。中学生と一緒に選手にタオルを渡す仕事したのですが、私だけ、英語が話せることを示すシールを胸元に貼っていたせいか、選手の多くが一番奥にいる私の元へ来てタオルが欲しいと言ってきました。立っていた位置の関係もあるのかもしれませんが、「English!」と言って近づいてきてくれる方もいました。シール1枚ではありますが、自分の能力を認めてもらえたようで嬉しかったです。
同時に言語を超えたつながりがスポーツにはあるのだと思いました。日本人選手が海外選手と交流をしている場面を何度か見ましたが、多少英語は話していましたが、トライアスロンという共通の文脈のあることで、ちょっとした声かけと笑顔だけで意思疎通が図れているのが印象的でした。普段は全く違う環境で暮らしている人たちが、スポーツという文化を介して同じ空間に集まっていることに面白さを感じました。
今年は事務局の方針でボランティアの募集期間が早まったため、本学からのボランティア参加は初日2名、2日目2名(各担当1名)と、少々寂しかったようです。一緒に活動する仲間がいると、お互い励まし合いながら、楽しく活動できるので、来年はぜひ多くの学生に参加してもらえることを願っています。
○選手との関わりを通して感じたことは、世界規模の場ではやはり英語が話せるというだけで周りからの扱いが変わるということです。中学生と一緒に選手にタオルを渡す仕事したのですが、私だけ、英語が話せることを示すシールを胸元に貼っていたせいか、選手の多くが一番奥にいる私の元へ来てタオルが欲しいと言ってきました。立っていた位置の関係もあるのかもしれませんが、「English!」と言って近づいてきてくれる方もいました。シール1枚ではありますが、自分の能力を認めてもらえたようで嬉しかったです。
同時に言語を超えたつながりがスポーツにはあるのだと思いました。日本人選手が海外選手と交流をしている場面を何度か見ましたが、多少英語は話していましたが、トライアスロンという共通の文脈のあることで、ちょっとした声かけと笑顔だけで意思疎通が図れているのが印象的でした。普段は全く違う環境で暮らしている人たちが、スポーツという文化を介して同じ空間に集まっていることに面白さを感じました。
今年は事務局の方針でボランティアの募集期間が早まったため、本学からのボランティア参加は初日2名、2日目2名(各担当1名)と、少々寂しかったようです。一緒に活動する仲間がいると、お互い励まし合いながら、楽しく活動できるので、来年はぜひ多くの学生に参加してもらえることを願っています。
(ボランティア支援室コーディネーター・柳本薫)



