大学院生 高桑 美央さんが、ANSCSE27でTHE BEST POSTER AWARD を受賞!
2024.09.27
- TOPICS
- 学生の活躍
量子化学国際会議ANSCSE27でJSTさくらサイエンスプログラムの共同研究成果を発表
生命ナノシステム科学研究科 博士後期課程1年(量子物理化学研究室)の高桑美央さんが、2024年7月30日〜8月3日にChulalongkorn University(タイ・バンコク)で開催されたThe 27th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE27)において、「Theoretical analysis of the influence of residues around the chromophore on Enhanced Green Fluorescent Protein」について発表し、THE BEST POSTER AWARD賞を受賞しました。
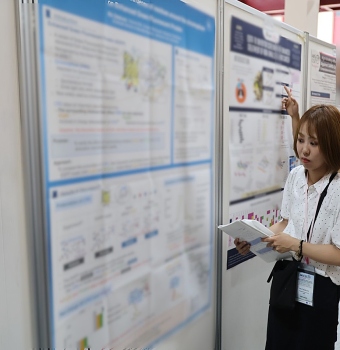 ポスター発表の様子。ポスター発表では、英語での質疑応答を流ちょうに行いました。
ポスター発表の様子。ポスター発表では、英語での質疑応答を流ちょうに行いました。
受賞者
生命ナノシステム科学研究科 博士後期課程1年
(量子物理化学研究室)
指導教員
生命ナノシステム科学研究科
立川 仁典 教授(量子科学・材料設計)
受賞内容
The 27th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE27)
THE BEST POSTER AWARD
発表題目
Theoretical analysis of the influence of residues around the chromophore on Enhanced Green Fluorescent Protein
高感度緑色蛍光タンパク質の発色団の周辺残基の影響に関する理論的解析
生命ナノシステム科学研究科 博士後期課程1年
(量子物理化学研究室)
高桑 美央 さん
指導教員
生命ナノシステム科学研究科
立川 仁典 教授(量子科学・材料設計)
受賞内容
The 27th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE27)
THE BEST POSTER AWARD
発表題目
Theoretical analysis of the influence of residues around the chromophore on Enhanced Green Fluorescent Protein
高感度緑色蛍光タンパク質の発色団の周辺残基の影響に関する理論的解析
今回の発表内容について高桑さんに解説していただきました。
緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein)は、緑色の蛍光を示すタンパク質であり、生きている生物内のタンパク質の動きを可視化できるツールとして生物学分野で広く利用されています。このタンパク質は、内部に「発色団」と呼ばれる色を示す部分があるため蛍光を示しますが、「発色団」の周辺のアミノ酸の詳細な役割は未解明でした。そこで私は理論計算を用いて、周辺のアミノ酸が与える影響を調べたところ、周辺の2つのアミノ酸が「発色団」の構造や発光に大きく影響していることが分かりました。
緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein)は、緑色の蛍光を示すタンパク質であり、生きている生物内のタンパク質の動きを可視化できるツールとして生物学分野で広く利用されています。このタンパク質は、内部に「発色団」と呼ばれる色を示す部分があるため蛍光を示しますが、「発色団」の周辺のアミノ酸の詳細な役割は未解明でした。そこで私は理論計算を用いて、周辺のアミノ酸が与える影響を調べたところ、周辺の2つのアミノ酸が「発色団」の構造や発光に大きく影響していることが分かりました。
高桑 美央さんのコメント
このたび、名誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。今回の発表は、私にとって初めての海外開催となる国際会議であり、とても緊張しました。英語での質疑応答やコミュニケーションの難しさを痛感しましたが、それが一層の学びと成長につながったと感じています。
この経験を励みに、今後もさらなる研究の発展に向けて努力を重ねてまいります。最後に、本研究の遂行や発表準備において、日頃からご指導いただいている量子物理化学研究室の立川仁典先生、島崎智実先生、北幸海先生、そして研究室の皆様に、この場を借りて心より御礼申し上げます。本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) および、JPMJSP2179 の支援を受けました。
このたび、名誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。今回の発表は、私にとって初めての海外開催となる国際会議であり、とても緊張しました。英語での質疑応答やコミュニケーションの難しさを痛感しましたが、それが一層の学びと成長につながったと感じています。
この経験を励みに、今後もさらなる研究の発展に向けて努力を重ねてまいります。最後に、本研究の遂行や発表準備において、日頃からご指導いただいている量子物理化学研究室の立川仁典先生、島崎智実先生、北幸海先生、そして研究室の皆様に、この場を借りて心より御礼申し上げます。本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) および、JPMJSP2179 の支援を受けました。
指導教員 立川 仁典教授のコメント
高桑さんの今回の受賞を、指導教員として大変うれしく思います。
高桑さんは、学部3年生の後期に北研究室に配属されてから、量子化学手法を用いてタンパク質の理論計算を精力的に取り組んできました。高桑さんは、他研究所の実験研究者とも積極的に議論し、今回の国際会議で発表した内容は、既に投稿論文として報告しております。またこの4月からは、本学のSPRINGフェローシップ にも採択され、今後のさらなる活躍を期待しています!
高桑さんの今回の受賞を、指導教員として大変うれしく思います。
高桑さんは、学部3年生の後期に北研究室に配属されてから、量子化学手法を用いてタンパク質の理論計算を精力的に取り組んできました。高桑さんは、他研究所の実験研究者とも積極的に議論し、今回の国際会議で発表した内容は、既に投稿論文として報告しております。またこの4月からは、本学のSPRINGフェローシップ にも採択され、今後のさらなる活躍を期待しています!
~JSTさくらサイエンスプログラムでの国際交流のひとこま~
量子物理化学研究室では、2024年1月14日~1月21日、ウボンラーチャターニー大学(タイ)、モンクット王工科大学ラートクラバン校(タイ)、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)から、大学生、大学院生、教員、計10名を招聘し、最先端マルチスケール量子水素シミュレーションを駆使した国際研究交流を実施しました。
研究室では、私が使用している電子だけでなく原子核の量子効果を考慮できる量子多成分系計算手法とそれらを使った結果について議論しました。
また、鎌倉の大仏や鶴岡八幡宮の観光を通じて日本文化を体感してもらいました。
詳細は、JSTさくらサイエンス 2023年度活動レポートをご覧ください。
https://ssp.jst.go.jp/report/2023/k_vol218.html
量子物理化学研究室では、2024年1月14日~1月21日、ウボンラーチャターニー大学(タイ)、モンクット王工科大学ラートクラバン校(タイ)、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)から、大学生、大学院生、教員、計10名を招聘し、最先端マルチスケール量子水素シミュレーションを駆使した国際研究交流を実施しました。
研究室では、私が使用している電子だけでなく原子核の量子効果を考慮できる量子多成分系計算手法とそれらを使った結果について議論しました。
また、鎌倉の大仏や鶴岡八幡宮の観光を通じて日本文化を体感してもらいました。
詳細は、JSTさくらサイエンス 2023年度活動レポートをご覧ください。
https://ssp.jst.go.jp/report/2023/k_vol218.html
 タイのモンクット王工科大学ラートクラバン校の学生さんとの交流の様子。1月のさくらサイエンスでタイから横浜市立大学に来てくれた、JayとFahが空港に見送りに来てくれました(左からFahさん、高桑さん、紀さん、坂上さん、Jayさん)
タイのモンクット王工科大学ラートクラバン校の学生さんとの交流の様子。1月のさくらサイエンスでタイから横浜市立大学に来てくれた、JayとFahが空港に見送りに来てくれました(左からFahさん、高桑さん、紀さん、坂上さん、Jayさん)


