地域と共に学び、未来を創る
後編 未来を共に描く
— 学生が地域に提案した解決策と学び
2025.10.09
- TOPICS
- 地域
- 国際商学部
国際商学部の学生たちが、地域の課題解決に挑んだ実践型授業「企画立案型実習B(金沢区版)」(担当教員:国際商学部 伊藤智明准教授 )。
金沢区をフィールドに進められた「企画立案型実習B」は、地域の金融機関や行政で活躍するゲスト講師との交流を通じ、地域課題や事業運営のリアルを学ぶことから始まりました。講義と現場での調査を経て、最終日には学生たちが自ら企画したプランを発表。実習での学びをどう形にし、地域の未来につなげたのか。その成果と学生の声をお届けします。
◀ 前編はこちら:https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20251008ito1.html
金沢区をフィールドに進められた「企画立案型実習B」は、地域の金融機関や行政で活躍するゲスト講師との交流を通じ、地域課題や事業運営のリアルを学ぶことから始まりました。講義と現場での調査を経て、最終日には学生たちが自ら企画したプランを発表。実習での学びをどう形にし、地域の未来につなげたのか。その成果と学生の声をお届けします。
◀ 前編はこちら:https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20251008ito1.html
 プレゼンテーションの様子 講義Day3
プレゼンテーションの様子 講義Day3
Day3:8月29日(金)@みなとみらいサテライトキャンパス
最終日は、これまでの学びや議論を集約し、各グループでプレゼンテーション資料の作成に取り組みました。資料をブラッシュアップしながらリハーサルを重ね、限られた時間の中で完成度を高めていきました。午後には、全6チームが順番に発表を行い、それぞれ独自の視点から地域課題への解決策を提案しました。学生たちの真剣な眼差しと達成感に満ちた表情が、このプログラムの充実ぶりを物語っていました。
各グループのプレゼンテーション内容
最終日は、これまでの学びや議論を集約し、各グループでプレゼンテーション資料の作成に取り組みました。資料をブラッシュアップしながらリハーサルを重ね、限られた時間の中で完成度を高めていきました。午後には、全6チームが順番に発表を行い、それぞれ独自の視点から地域課題への解決策を提案しました。学生たちの真剣な眼差しと達成感に満ちた表情が、このプログラムの充実ぶりを物語っていました。
各グループのプレゼンテーション内容
グループ1:自転車専用道路・シェアサイクル設置による人の流れの活性化
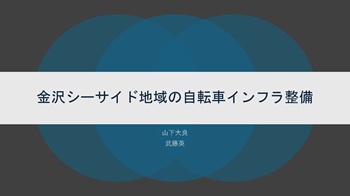
金沢区の地域課題として、あしたタウンラボでのインタビューや自身の経験から、「交通の便の悪さ」が挙げられました。地域活性化には人の流れが不可欠であり、人がお金を使うことで経済が循環します。そこで、地域住民の日常生活における行動範囲の拡大や、八景島シーパラダイスや三井アウトレットパークなどを訪れる外部の人の流れを金沢区全体に広げることが重要だと考えました。その解決策として、自転車専用道路やシェアサイクルの導入を提案しました。これにより、飲食店や娯楽施設の利用が増え、金沢区がさらに魅力的で住みやすい街になることを期待しています。
グループ2:多言語表記やホワイトボード設置による異文化間トラブル解消
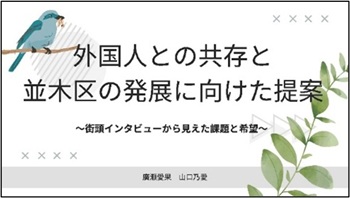
海外にルーツを持つ住民が増えている一方で、受け入れる体制が十分に整っておらず、近隣住民とのトラブルにつながっているという課題に着目しました。金沢区について学ぶ中で、若者の転入と定住の促進が重要であること、また海外にルーツを持つ住民へのサポートが不足していることに気づいたからです。そこで、こうした気づきをもとにフィールドワークを実施しました。現場での調査から、「言語や文化の違い」によって、トイレやゴミ捨て場などの利用をめぐるトラブルに悩む地域住民がいることを知りました。この問題を解決するため、私たちはトイレやゴミ箱、掲示板などに日本語だけでなく英語などの多言語表記を導入し、多言語で情報共有できるホワイトボードの設置を提案しました。この取り組みを起点として、異なる言語や文化を持つ住民同士のコミュニケーションが活性化し、交流の場が広がっていくことを期待しています。
グループ3:自動運転バス導入と社宅提供による職住近接と交通利便性向上
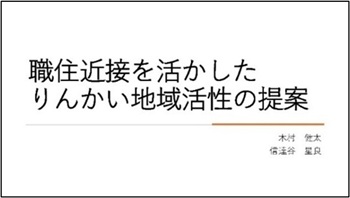
私たちは、りんかい地域で働く人々や居住者へのインタビューを通じて、交通の利便性の低下と街の活気の喪失が地域課題であると捉えました。そこで、自動運転バスの導入と、働く人々への社宅の提供を提案します。りんかい地区と並木地区を結び、働きやすく住みやすい「職住近接」の環境を実現します。
縦方向の移動には電車、横方向の移動にはバスを活用することで、外部へのアクセス性を高め、地域全体の利便性を向上させることが可能です。さらに将来的には、早朝や深夜帯にも運航ダイヤを設定できるため、運輸・通信業の比率が高まるりんかい地区において、働く人々向けの社宅需要も期待できます。加えて、金沢シーサイドラインとの連携により、公共交通機関の自動化を推進するモデルタウンとしての付加価値も高まると考えます。
縦方向の移動には電車、横方向の移動にはバスを活用することで、外部へのアクセス性を高め、地域全体の利便性を向上させることが可能です。さらに将来的には、早朝や深夜帯にも運航ダイヤを設定できるため、運輸・通信業の比率が高まるりんかい地区において、働く人々向けの社宅需要も期待できます。加えて、金沢シーサイドラインとの連携により、公共交通機関の自動化を推進するモデルタウンとしての付加価値も高まると考えます。
グループ4:子育て世帯向け広報・SNS発信で人口減少抑制
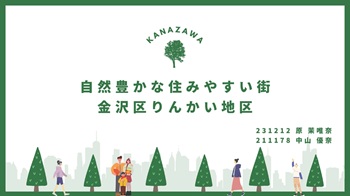
私たちは、金沢区りんかい地区における人口減少を重要な課題と捉え、その解決に向けて「金沢区りんかい地区の人口減少にブレーキをかける」という目標を掲げました。講義とヒアリングを通じて、同地区には多くの都市施設が整備されており、子育てに適した環境があるにもかかわらず、人口が減少している現状を知りました。そこで、子育てに最適なまちとしての魅力を広く伝えたいと考えました。
今回の提案では、妊娠・出産に伴い引越しを検討している方々をターゲットに、市内の役所と提携し、妊娠・出産時の助成金や給付金の申請に訪れた方々に対して、子育てに適した地域を紹介する「子育てマガジン」の作成・配布を行うこと、またインスタグラムなどのSNSを活用して魅力を発信することを提案します。
この取り組みを通じて、人口減少へのアプローチを図るとともに、地域活動の活性化、都市施設の有効活用、そして循環的な繁栄へとつなげていきたいと考えています。
今回の提案では、妊娠・出産に伴い引越しを検討している方々をターゲットに、市内の役所と提携し、妊娠・出産時の助成金や給付金の申請に訪れた方々に対して、子育てに適した地域を紹介する「子育てマガジン」の作成・配布を行うこと、またインスタグラムなどのSNSを活用して魅力を発信することを提案します。
この取り組みを通じて、人口減少へのアプローチを図るとともに、地域活動の活性化、都市施設の有効活用、そして循環的な繁栄へとつなげていきたいと考えています。
グループ5:モルック大会などイベント開催とSNS発信による地域活性化
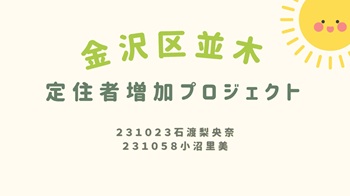
私たちは金沢区並木地域において、「子どもの遊び場の少なさ」と「人口減少」を課題として取り上げました。地域住民への取材を通じ、若者の姿が少ないこと、そして子どもたちが自由に遊べる場所が限られており、地域の魅力や活気が十分に発揮されていないと感じたためです。この課題を解決する方法として、地域イベントの拡充を提案しました。具体的には、横浜市立大学のモルックサークルと協力し、モルック大会を開催します。モルックは年齢や性別を超えてチームを組めるため、地域住民が誰でも参加できるのが特徴です。
さらに、このようなイベント開催と同時に、SNSや電車内広告を活用して地域の魅力を広く発信していきたいと考えています。
さらに、このようなイベント開催と同時に、SNSや電車内広告を活用して地域の魅力を広く発信していきたいと考えています。
グループ6:「金沢区を再発見する」ツアーによる地域愛着・移住定住促進

授業での地域団体や金融機関、行政関係者の講演や地域住民へのインタビューを通じて、金沢区には歴史や自然、工業地帯などさまざまな魅力がある一方で、その認知不足や高齢化、工業地帯の人手不足といった課題があることが分かりました。そこで私たちは「金沢区を再発見する」をテーマに、金沢区の歴史スポットと自然を巡り、その魅力を体感できるツアーの開催を提案しました。ツアーを通じて、地域の方々には地域の愛着を深める機会を、観光客には金沢区の魅力を知ってもらう機会を提供し、移住・定住の促進を通じて工業地帯の人手不足解消にもつなげたいと考えています。
今後も1つの取り組みから幅広い価値を生み出せるような金沢区の地域活性化活動に取り組んでいきたいです。
講義に参加した学生のコメント
今後も1つの取り組みから幅広い価値を生み出せるような金沢区の地域活性化活動に取り組んでいきたいです。
講義に参加した学生のコメント
 黒羽 葵衣さん
黒羽 葵衣さん
黒羽 葵衣さん
講義を通して、普段通学している横浜市金沢区について深く知ることができました。地域団体や行政、金融機関の方々にご講演いただき、さらに地域住民の声も直接伺うことで、金沢区の魅力や課題について多角的に学ぶ貴重な機会となりました。課題に対して提案を行ったため、知識を得るだけでなく、その知識を活かして実際に企画するプロセスも一度に経験することができました。私は現在、ゼミで横浜市金沢区の地域活性化に取り組んでいるため、今回得た知識や学びをその活動に活かしたいと考えています。3日で金沢区に詳しくなれる授業であり、今まで以上に金沢区に親しみを持てるようになる実習だと思いました。
講義を通して、普段通学している横浜市金沢区について深く知ることができました。地域団体や行政、金融機関の方々にご講演いただき、さらに地域住民の声も直接伺うことで、金沢区の魅力や課題について多角的に学ぶ貴重な機会となりました。課題に対して提案を行ったため、知識を得るだけでなく、その知識を活かして実際に企画するプロセスも一度に経験することができました。私は現在、ゼミで横浜市金沢区の地域活性化に取り組んでいるため、今回得た知識や学びをその活動に活かしたいと考えています。3日で金沢区に詳しくなれる授業であり、今まで以上に金沢区に親しみを持てるようになる実習だと思いました。
 山下 大良さん
山下 大良さん
山下 大良さん
普段、大学の授業で学んでいることを実際に活かして考える機会は多くありません。机上の学びにとどまると感じる人も少なくないと思います。この授業では、実際に企画立案を行うことで、これまで学んできた知識やスキルを使う場になりました。
同時に、その知識を活用して自分のアイデアを形にすることの難しさを実感しました。学部で学ぶ内容は、基礎にすぎず、それを応用する力が今後求められることを痛感しました。その第一歩を踏み出す場としてこの授業は非常に良い機会になりました。学生主体で授業が進み、少人数のためお互いに活発に意見交換できました。かき氷を楽しみながら学んだ3日間は、充実した経験となりました。
普段、大学の授業で学んでいることを実際に活かして考える機会は多くありません。机上の学びにとどまると感じる人も少なくないと思います。この授業では、実際に企画立案を行うことで、これまで学んできた知識やスキルを使う場になりました。
同時に、その知識を活用して自分のアイデアを形にすることの難しさを実感しました。学部で学ぶ内容は、基礎にすぎず、それを応用する力が今後求められることを痛感しました。その第一歩を踏み出す場としてこの授業は非常に良い機会になりました。学生主体で授業が進み、少人数のためお互いに活発に意見交換できました。かき氷を楽しみながら学んだ3日間は、充実した経験となりました。
 左から山口さん、廣瀬さん
左から山口さん、廣瀬さん
廣瀬 愛果さん
横浜市立大学に通っていながら、金沢区について知る機会はほとんどありませんでしたが、この授業を通して理解を深めることができ、貴重な経験となりました。これまでの授業では、学生自身が考え、計画し、行動するような内容はなく、良い意味で刺激的で学びの多い授業でした。2日目のインタビューでは、相手を自分たちで探す必要があり、初めは苦戦しましたが、地元の方々と多く触れ合うことで、温かい気持ちになりました。受講者数も比較的少なかったため、学生同士で協力し合い、かき氷を作ったことも良い思い出です。自主的に行動できる場を用意していただき、多くの学びを得ることができました。来年以降もこの授業があれば、ぜひ受講をお勧めしたいです。
横浜市立大学に通っていながら、金沢区について知る機会はほとんどありませんでしたが、この授業を通して理解を深めることができ、貴重な経験となりました。これまでの授業では、学生自身が考え、計画し、行動するような内容はなく、良い意味で刺激的で学びの多い授業でした。2日目のインタビューでは、相手を自分たちで探す必要があり、初めは苦戦しましたが、地元の方々と多く触れ合うことで、温かい気持ちになりました。受講者数も比較的少なかったため、学生同士で協力し合い、かき氷を作ったことも良い思い出です。自主的に行動できる場を用意していただき、多くの学びを得ることができました。来年以降もこの授業があれば、ぜひ受講をお勧めしたいです。
山口 乃愛さん
3日間という短い期間でしたが、非日常な体験を通して、久しぶりに生き生きとした日々を過ごせたと感じました。私は、人に話しかけることが苦手なのですが、この授業では声をかけなければ課題を見つけられず、グループの振興にも支障をきたす状況だったため、積極的かつ能動的に行動する必要がありました。その結果、声をかけに行くことへの恐怖が薄れ、少し強くなれた気がします。この活動は、将来社会人として働く際にも役立つ経験になると思います。さまざまな仲間と刺激し合いながら取り組めたことは、自身の成長につながる良い機会でした。来年度、さらにパワーアップした企画が見られることを楽しみにしています。
3日間という短い期間でしたが、非日常な体験を通して、久しぶりに生き生きとした日々を過ごせたと感じました。私は、人に話しかけることが苦手なのですが、この授業では声をかけなければ課題を見つけられず、グループの振興にも支障をきたす状況だったため、積極的かつ能動的に行動する必要がありました。その結果、声をかけに行くことへの恐怖が薄れ、少し強くなれた気がします。この活動は、将来社会人として働く際にも役立つ経験になると思います。さまざまな仲間と刺激し合いながら取り組めたことは、自身の成長につながる良い機会でした。来年度、さらにパワーアップした企画が見られることを楽しみにしています。

教員のコメント
伊藤智明先生(国際商学部/担当教員)
企画立案型実習B(金沢区版)を担当するようになって、今年度で2年が経過したことになります。この2年間で考え続けているのは、「横浜や金沢という地域で私たちにどんな貢献ができるのか」ということです。地域の方々のご協力や受講生の参加のおかげで地域を知り、地域で交流し、地域のために活動する、という本講義の型をつくることができました。誠にありがとうございます。来年には、さらなる改善を重ねた企画立案型実習Bの姿をお見せいたします。今後ともご協力の程何卒よろしくお願いいたします。
伊藤智明先生(国際商学部/担当教員)
企画立案型実習B(金沢区版)を担当するようになって、今年度で2年が経過したことになります。この2年間で考え続けているのは、「横浜や金沢という地域で私たちにどんな貢献ができるのか」ということです。地域の方々のご協力や受講生の参加のおかげで地域を知り、地域で交流し、地域のために活動する、という本講義の型をつくることができました。誠にありがとうございます。来年には、さらなる改善を重ねた企画立案型実習Bの姿をお見せいたします。今後ともご協力の程何卒よろしくお願いいたします。
今回の「企画立案型実習B」は、単なる講義にとどまらず、学生と地域が出会い、対話し、未来を共に考える場となりました。






