生命医科学研究科の明石知子教授が、日本質量分析学会 学会賞を受賞!
2025.07.29
- TOPICS
- 研究
- 理学部
生命現象の解明へ! 生体高分子の「ありのまま」を捉えるネイティブ質量分析法による研究が表彰
生命医科学研究科の明石知子教授が、2025年6月22日(日)にANAインターナショナル石垣リゾートで行われた第10回アジア・オセアニア質量分析会議(2025年6月22日~25日)に付随して行われた2025年度日本質量分析学会総会で、日本質量分析学会学会賞を受賞しました。

今回の受賞研究内容について明石先生に解説していただきました。
タンパク質等の生体高分子は、その特定の立体構造(高次構造*3)や、他の分子との結合によって形成される複合体こそが、生命活動における多様な機能を発揮する上で不可欠です。タンパク質を一般的な方法で質量分析する場合、微量なサンプルを高感度に分析することに主眼が置かれています。この方法では、サンプルを酸性条件や有機溶媒を含む溶液で調製するので、タンパク質等の高次構造が崩れたり、特異的に形成された複合体が解離したりしてしまいます。そのため、機能に重要な「ありのままの形」での情報取得は困難でした。そこで私は、1990年代より、生体内での現象をより忠実に反映した分析を目指し、非変性条件下で質量分析を行う「ネイティブ質量分析法」の研究を幅広く展開してきました。この手法は、分析感度においては不利ではありますが、タンパク質などの高次構造や、特異的に形成される複合体の構造情報を保持したまま、質量分析で解析することを可能にします。
この「ネイティブ質量分析法」によって得られる情報は、生体高分子の機能メカニズムを理解する上で極めて有用です。最近では、世界で初めて“一細胞ネイティブ質量分析”にも成功するなど、その技術は進化を続けています(詳しくはこちらの記者発表記事をご覧ください) 。長年にわたるこのような先駆的な研究業績と、生命科学分野における貢献が認められ、今回の日本質量分析学会 学会賞の受賞に至りました。
タンパク質等の生体高分子は、その特定の立体構造(高次構造*3)や、他の分子との結合によって形成される複合体こそが、生命活動における多様な機能を発揮する上で不可欠です。タンパク質を一般的な方法で質量分析する場合、微量なサンプルを高感度に分析することに主眼が置かれています。この方法では、サンプルを酸性条件や有機溶媒を含む溶液で調製するので、タンパク質等の高次構造が崩れたり、特異的に形成された複合体が解離したりしてしまいます。そのため、機能に重要な「ありのままの形」での情報取得は困難でした。そこで私は、1990年代より、生体内での現象をより忠実に反映した分析を目指し、非変性条件下で質量分析を行う「ネイティブ質量分析法」の研究を幅広く展開してきました。この手法は、分析感度においては不利ではありますが、タンパク質などの高次構造や、特異的に形成される複合体の構造情報を保持したまま、質量分析で解析することを可能にします。
この「ネイティブ質量分析法」によって得られる情報は、生体高分子の機能メカニズムを理解する上で極めて有用です。最近では、世界で初めて“一細胞ネイティブ質量分析”にも成功するなど、その技術は進化を続けています(詳しくはこちらの記者発表記事をご覧ください) 。長年にわたるこのような先駆的な研究業績と、生命科学分野における貢献が認められ、今回の日本質量分析学会 学会賞の受賞に至りました。
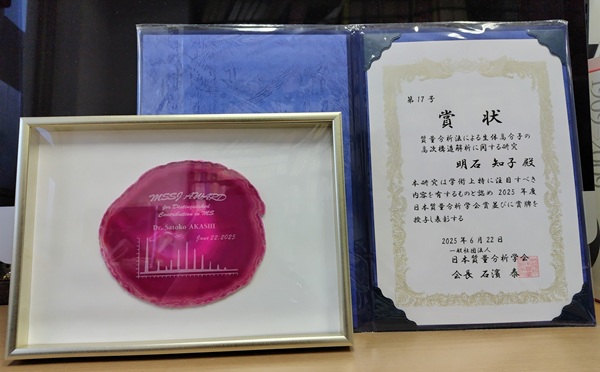 日本質量分析学会 学会賞の賞状(右)と賞牌(左)
日本質量分析学会 学会賞の賞状(右)と賞牌(左)
明石教授に受賞のコメントをいただきました
このたび、日本質量分析学会から学会賞という最高の栄誉を賜り、大変光栄に存じます。これを励みとして、さらに自身の研究活動と、日本における質量分析研究のさらなる発展に尽力するとともに、その成果を社会に還元し、広く情報発信に努めてまいりたいと考えております。今回の受賞対象となった研究業績を積み重ねるにあたり、これまでご指導いただいた諸先生方、ご協力いただいた学内外の共同研究者の皆さま、そして研究室の学生やスタッフの皆さまに、心より感謝申し上げます。
このたび、日本質量分析学会から学会賞という最高の栄誉を賜り、大変光栄に存じます。これを励みとして、さらに自身の研究活動と、日本における質量分析研究のさらなる発展に尽力するとともに、その成果を社会に還元し、広く情報発信に努めてまいりたいと考えております。今回の受賞対象となった研究業績を積み重ねるにあたり、これまでご指導いただいた諸先生方、ご協力いただいた学内外の共同研究者の皆さま、そして研究室の学生やスタッフの皆さまに、心より感謝申し上げます。
用語説明
*1 質量分析法:原子や分子を気体状のイオンにして、電場や磁場の中を運動させ、その様子を測定することにより、試料の質量を求める方法。
*2 生体高分子:タンパク質や核酸(DNA、RNA)等、生命活動に重要な役割を果たす、分子量が1万を超えるような巨大な分子。
*3 高次構造:タンパク質や核酸などの生体高分子では、一次構造がアミノ酸や塩基の配列を意味するのに対し、高次構造は分子全体の立体的な配置や形状を意味し、生体内での 機能を発揮する際に特に重要なものである。そのため、例えば、医薬品開発では品質管理や安全性評価に不可欠な情報である。
*1 質量分析法:原子や分子を気体状のイオンにして、電場や磁場の中を運動させ、その様子を測定することにより、試料の質量を求める方法。
*2 生体高分子:タンパク質や核酸(DNA、RNA)等、生命活動に重要な役割を果たす、分子量が1万を超えるような巨大な分子。
*3 高次構造:タンパク質や核酸などの生体高分子では、一次構造がアミノ酸や塩基の配列を意味するのに対し、高次構造は分子全体の立体的な配置や形状を意味し、生体内での 機能を発揮する際に特に重要なものである。そのため、例えば、医薬品開発では品質管理や安全性評価に不可欠な情報である。


