【国際教養学部 座談会】
模擬アフリカ連合会議に挑戦!
~日本からアフリカの未来を考える~

(プロフィール)
写真左から
国際教養学部 西海 洋志 准教授(国際関係論)
国際教養学部 国際教養学科2年 東島 ことほ さん
国際教養学部 国際教養学科2年 ベンアブダラ テス二ム さん
国際教養学部 国際教養学科2年 久保 美紀さん
国際教養学部 国際教養学科2年 リズワン ウッメ ハニー さん
2025年に横浜で TICAD(アフリカ開発会議)が開催されます。それに向けて今年8月に、日本の大学生や留学生が集まり、アフリカの課題について議論する模擬アフリカ連合(AU)会議が開催されました。この会議は、学生有志が中心となって企画し、国際協力機構(JICA)や国連開発計画(UNDP)などの支援を受けて実現しました。本学からこの模擬AU会議に参加した学生4人と西海洋志准教授に、この経験で得られたことやこれからの目標など、詳しく話を聞きました。
それぞれの興味・関心ごと
——学生の皆さんのことを教えてください。
東島 西海先生のゼミに所属しています。英語は得意な方ですが、留学生会で友達を作って、英語を使う機会を増やしています。
ベンアブダラ 出身はチュニジアです。3歳で日本に来て、幼稚園から高校までずっと日本の教育を受けて育ち、一度チュニジアに戻って、2011年からまた日本で生活しています。
久保 沖縄県出身で、大学で初めて横浜に来ました。他県への移動は飛行機が必要だったので、陸続きなのはとても便利ですね。
リズワン 私の両親の国籍はパキスタンですが、私と兄弟みんな横浜で生まれて育ちました。横浜が大好きで、国際教養学部の鈴木伸治 教授のゼミでは、新しい視点で横浜のまちを知ることができて刺激を受けています。
——ベンアブダラさんとリズワンさんは日本で育って、日本人と同じ入試制度でYCUに入学したんですね。
リズワン はい、私はAO入試(当時)で、高校の活動をフリップにまとめてプレゼンしました。
ベンアブダラ 私も同じくAO入試で、「7カ国語が話せます」とアピールしました。家族とは、チュニジアの母国語のアラビア語とフランス語で話します。日本語と英語の他に、スペイン語、ロシア語と韓国語も、その国の友だちと会話したり、自分で勉強したりして覚えました。
——模擬AU会議に参加しようと思ったきっかけを教えてください。
東島 もともとアフリカに興味があり、学生団体「TEHs(テフズ)」の古着プロジェクトに関わったことで、アフリカの古着問題に興味をもちました。一度、日本模擬国連日吉研究会(以下、模擬国連)に参加したことがあったのですが、西海先生から模擬AU会議の開催を教えていただき、再度チャレンジしたいと思い参加しました。
ベンアブダラ 1年生から模擬国連で活動をしていて、アフリカ連合(AU)の仕組みとその課題について知りたいという純粋な好奇心でした。また、チュニジア人としてアフリカの問題について深く考えたいという思いもありました。


久保 東島さんが声をかけてくれたことがきっかけでした。1年生のときに模擬国連に参加したことがあったのですが、また、こんなチャンスがいつあるか分からないと思って、この機会にチャレンジしようと思って参加しました。
リズワン 大学の都市学系での学びを進める中で、実際に環境問題に対してどのような対策を打ち出すのかということを経験してみたいと思い、興味を持ちました。こういった会議に参加するのは初めてでした!


世界への扉を開く貴重な経験
模擬AU会議では、アフリカ諸国が協力して問題解決に向けた決議を採択することを目指します。参加者は、アフリカ各国の代表者になりきって会議に参加します。それによって、担当国のことやアフリカ諸国間の関係、また、アフリカ諸国と国際社会の関係を、自分自身の課題として捉え直し、より深く詳細に学ぶことができます。
——実際に、模擬AU会議に参加してみてどうでしたか?
久保 私は東島さんとペアで、スーダンの代表を務めました。参加者との活発な議論の中で、最初は意見が対立することもありましたが、互いの立場を理解し、協力することで、最終的に合意に達することができました。
東島 スーダンの代表ということで、アフリカの紛争や気候変動問題について調べました。その中で、気候変動が紛争につながる、という事実を知り衝撃を受けました。また、紛争をしている国は、難民が発生する国 である同時に、難民受け入れ国でもある、という複雑な現実も学びました。紛争をしている国を責めるだけでは何の解決にもならず、その国がどのような状況に置かれているのか理解する姿勢を持つことが必要だと思いました。
リズワン 私はベンアブダラさんとペアで、チュニジアの代表を務めました。午前中は、自国の意見や、国の代表として客観的な意見が言えたと感じております。沢山の意見を発言をしたおかげで、自国の意見が取り入れられなくても、納得した結果を残せました。
ベンアブダラ 自分がこれまで経験したことがある模擬国連より、多くの国の参加があったので、それぞれの意向を知ることができたことがとても勉強になりました。英語で交渉する場面では相手を説得することに加えて、相手の意見を聞くことでとても考えさせられました。模擬国連ではスイスのような永世中立国を代表することが多く、アフリカの国ごとの経済問題など、アフリカ視点で議論する機会は少なかったです。しかし、今回の模擬AU会議では、アフリカ諸国の具体的な問題について、アフリカ人としての視点を持って議論することができました。模擬国連がマクロな視点で国際問題全体を捉えるのに対し、模擬AU会議はよりミクロな視点で、特定地域の問題に深く掘り下げて考えることができました。

模擬AU会議に向けた準備は大変だった!
模擬AU会議は、ただ自国の意見を述べるだけではなく、他の参加国と交渉し、合意点を見つけることが求められるので、自分の国の立場を深く理解し、相手の国の状況も把握しておく必要がありました。模擬AU会議の準備は、授業のレポートより大変だったそうです。
久保 ペアになった2人で担当する国の歴史、政治、経済、社会問題、他国との関係性など、あらゆる角度から徹底的に調べました。
東島 普段からニュースを見て世界の問題に関心はあったものの、表面的な部分しか見ていなかったと思いました。模擬AU会議に参加したことで、各国が国際舞台でどのように振る舞っているのか、その裏側にある本音と建前を知ることが必要なのではないかと思いました。
ベンアブダラ アフリカのそれぞれの国に関する日本語の資料は少なく、フランス語の資料を翻訳したり、大使館に直接問い合わせたりと、様々な方法で情報を集めました。
リズワン 準備は本当に大変でした。でもその準備をしたことで、本番でしっかりと議論することができました。大人の世界では、利益や自国中心の考えが優先されると思うけれど、学生はより広い視野を持って問題解決を客観的に考えることができたのではないかと思います。小さなグループでの話し合いでは、一人ひとりの意見を尊重し、全員が納得するまで議論を進めることができました。
西海 模擬AU会議は今回が初めての開催でしたが、自分たちの力で問題解決に貢献できるという実感を得ることができ、より希望を感じることができた点で、意義があったと皆さんの話をきいて実感しました。
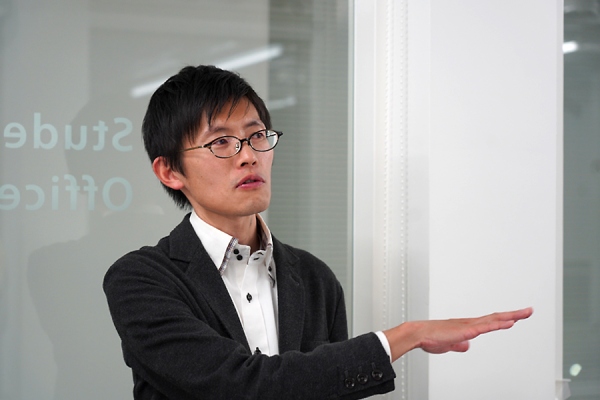
今後に向けて
——YCUで特に興味をもって学んでいることや、これからもっと学んでみたい(研究してみたい)ことを教えてください。
リズワン 日本に在住している外国人コミュニティが抱える問題に対して、どのような対策を行い、街を活性化し共存できる都市や社会を作るかということに興味をもっています。これから、様々な立場の方の意見を聞いて研究したいです。
ベンアブダラ 国際関係学を学び、特に紛争問題、とりわけ難民問題に強い関心を抱いています。今話題になっているパレスチナ問題にも注目していて、国際関係学的なアプローチで解決策を探求したいと考えています。
久保 柿崎一郎 教授のゼミに所属していて、東南アジアなど国際問題に関心をもっています。具体的なテーマはこれから考えていくところです。
東島 ホロコースト におけるロマの人々に関心があります。ホロコースト下では、ユダヤ人の他に、ロマの人々や性的マイノリティ、精神疾患のある人なども犠牲になりました。犠牲者の中にヒエラルキーができたり、非ユダヤ人に対して罪の意識や関心が希薄であったりと、日本ではあまり知られていない歴史に興味をもちました。1970年代前後のヨーロッパ諸国の政府の戦後補償にも注目したいと考えています。
西海 大学のゼミの活動では、指導教員の専門分野ではないものでも、学生の興味のあるテーマを取り上げるようにしています。いろいろなことに関心をもってほしいですね。

——この経験を生かした将来の展望を教えてください。
リズワン ゼミは都市学系で、副ゼミを教養学系にして、教師になることを目指して教職課程も履修しています。自分の経験を子どもたちに伝えて、もっと子どもたちの選択肢を増やしたいと思っています。横浜の都市問題を解決するために、フィールドワークを行いながら、具体的な活動を行っていきたいと考えています。例えば、横浜の地域住民と協力して、地域の問題解決に取り組んだり、横浜の魅力を国内外に発信する活動を行ったりするなど、様々な可能性を模索しています。
また模擬国連や模擬AU会議に参加して、社会の問題に対して何か貢献したいと思うようになりました。就職をしても、社会参加や様々なチャレンジをしていきたいです。
久保 今回の経験を通して、世界が抱える問題について深く考えるようになりました。会議で議論するだけでなく、実際に問題を抱えている地域を訪れ、人々と直接関わってみたいです。以前、タイの学校のボランティア活動を訪問した際、国際協力の現場で働く人々の熱意や、支援を必要としている人々の笑顔に直接触れ、国際協力の仕事に魅力を感じました。今後もこのような活動を通じて、社会に貢献したいと考えていまです。
東島 来年、長期留学をしたいと考えています。英語圏以外の国への渡航を視野に入れて交換留学への準備を進めています。大学の専門外国語の授業でフランス語を選択していて、日常会話ができるようにがんばっています。
ベンアブダラ 高校生の頃から国際連合で働きたいという夢があります。大学に入ってから模擬国連に参加し、実際に国際交渉を体験することで、国際関係の仕事の魅力を強く感じています。
特に教育を十分に受けられない子供達に初等教育を受けられる場を作りたいと考えています。紛争や迫害、極度の貧困を逃れて難民や移民となった子供たちへの教育支援がとても重要だと思っています。教育は人々に希望を与えることができると思うので、教育を通じて難民の子供たちが明るい未来を築けるよう、実際に現場に足を運び、難民支援の活動を通して国際社会に貢献したいです。
自分のルーツであるチュニジアと、生まれ育った日本の両方の視点を持つことができるという強みを活かして、国際的な問題解決に貢献したいと考えています。そのため、語学力を磨くとともに、国際関係に関する知識を深めていくつもりです。
YCUで未来への扉を開こう!
——YCUを目指している受験生に向けてのメッセージをお願いします。

友達や先輩から日々様々な刺激を受けています。この環境にいるからこそ、興味のあることに対して行動したり、新しい分野に興味を持ったりすることができると思います。
人生の中で何か一つのことを極めることも大事だけれども、たくさんの経験も同じくらい大事だと感じています。たとえ周りと比べて自分が成果を出せてなくても、後々役立つのは結果ではなく『経験値』です。結果だけにとらわれず、たくさん経験をしましょう! YCUにはいろいろな選択肢があって、経験ができます。
夢はたくさんみてほしいです。今やりたいことがある人も決まっていない人も、YCUに来れば、いろいろな授業、ゼミ活動や課外活動などでやりたいことを見つけられます。YCUで学ぶ自分の姿を想像しながら自分の力を信じて頑張ってほしいです。応援しています!

——西海先生から学生へのエールと今後の期待を聞かせてください。
西海 学生の活動は、社会全体を変えるきっかけになる可能性を秘めていると思います。未来は自分たちの行動から変えられると勇気をもって行動できるように、学生が一歩踏み出すきっかけとなる機会を提供したいと考えています。そして、学生たちが積極的に活動に参加することで、大学全体が活気あふれる場所になることを期待しています。
横浜市立大学では、国際問題に関心を持つ学生の学びを応援しています。国際教養学部には教養学系と都市学系があり、国際関係論や地域研究など、幅広い分野を学ぶことができます。多様なバックグラウンドを持つ学生たちと交流し、共に成長できる環境があります。
(2024/12/6)
