

「におい」を探究して
消費者の課題を解決したい
今の仕事を選んだ理由やきっかけを教えてください
さまざまな製品を扱っているメーカーなので、身に付けた知識や技術を幅広く活用できると考えて選びました。就職活動では、化粧品メーカーや香料メーカーに興味を持ち、研究職として活躍したいという思いから、積極的に業界の学会に参加したり、OB訪問をしたりしました。そのなかで、花王の技術力や先輩社員のキャリアに魅力を感じ、ここでさまざまな経験を積みながら技術を身に付け、生活者の不満解消に貢献できる研究者になりたいと考えました。
現在の主な業務内容について、教えてください
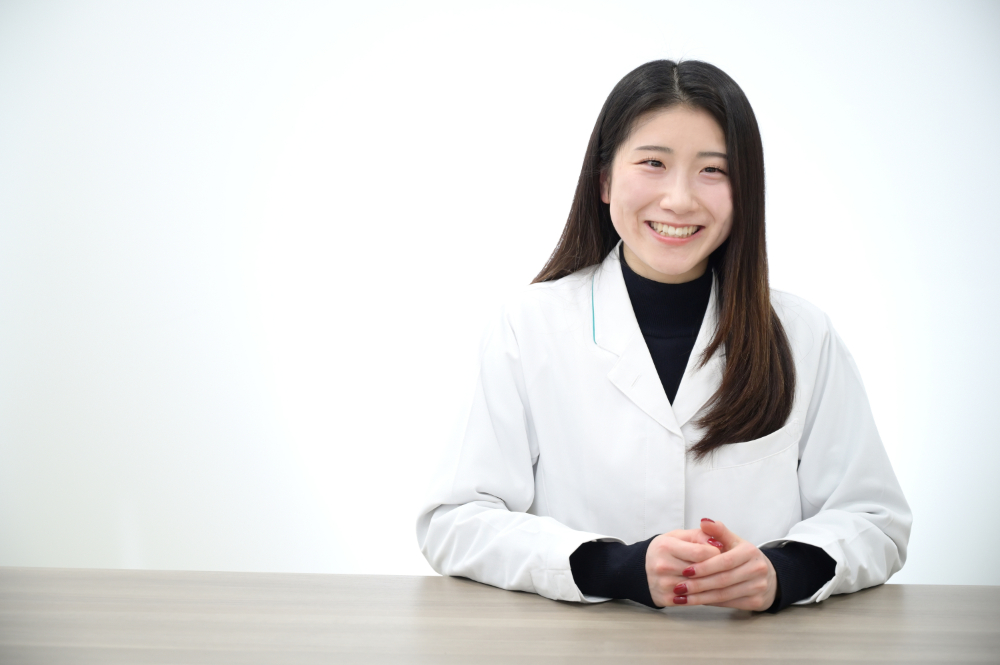
研究開発部門で、「価値を実感できる感覚体験や感性情報をもとにした技術開発」を行う部署に所属し、においの分析を担当しています。においには、いい香りもあれば、不快ないわゆる「悪臭」もあります。私は特に悪臭の研究をテーマにしており、洗剤や消臭剤、柔軟剤などの開発につながる基礎研究を行っています。
においは人によって感じ方が異なり、数値で測るのが難しいため、専門的な知識が必要な分野です。しかし、快適な生活のために重要な研究でもあります。私は、生活環境で起きているにおいの問題を理解し、それを解決する技術を開発し、製品に応用されることを目標にしています。
業務において、「大変なこと」や「やりがい」を教えてください
「起きる現象を理解し探求する」という研究への向き合い方は、学生時代と変わりませんが、社会人になってからは研究の進め方を変える必要があると感じました。一つの仕事に多くの人が関わるため、優先順位を決めて進めることが求められ、入社当初は苦労しました。年齢の離れた上司たちと一緒に働くことも学生時代とは大きく異なる点ですが、知識も技術も豊富に携えた先輩方から日々学び、刺激を受けています。
また、学生時代は研究の対象が学問的な探求でしたが、今は研究の先にある「消費者にどう貢献できるか」を常に考える必要があります。しかし、最終的に消費者のためになるという目標があるからこそ、研究が人の生活に役立つ実感があり、それが大きなやりがいにつながっています。

YCUを選んだ経緯について、教えてください
高校時代、将来やりたいことがはっきりせず、進路に悩んでいました。そんなとき、担任の先生から「今決めなくても、大学に入って視野を広げながら考えればいい」とアドバイスを受け、YCUを勧められました。調べてみると、語学に力を入れていることや、学べることの選択肢が多く、幅広く学びながら自分の興味を見つけられる環境に魅力を感じました。また、小規模で教授との距離が近く、相談しやすい雰囲気も自分に合っていると感じました。
学生時代、特に力を入れた学びは何ですか?
学生時代は、研究活動に特に力を入れていました。3年の後期から関本奏子 先生のもと、質量分析研究室で研究を始めました。もともと質量分析の分野に興味があり、授業で学んだときに「パズルのようにバラバラなものを組み合わせて、ひとつの正解にたどり着く」という過程がとても面白く、ワクワクしたのを覚えています。
研究テーマは、「香り成分の測定における新規技術の応用」です。この研究では、データを一つひとつ丁寧に解析するという地道な作業が必要で、時間も労力もかかりました。それだけに、学会や研究発表会で評価されたときの喜びは大きかったです。特に、「第34回におい・かおり環境学会」でベストプレゼンテーション賞を受賞したことは、自分の研究が評価されたと実感でき、大きな達成感につながりました。
さらに研究を深めたくて大学院に進学しました。ここでも関本先生が親身に指導してくださり、修士論文発表では優秀賞を受賞しました。研究を通じて自分のやりたいことが明確になり、とても価値ある経験でした。
YCUでの経験が、現在に役立っていると感じることはありますか?
何事にも貪欲に向き合える姿勢は、YCUでの経験を通じて身に付いたものだと感じています。研究活動はもちろんですが、PE(Practical English)の単位取得に必要なTOEICのスコアに向き合ったことも大きな経験でした。一定のスコアが進級の条件だったため、語学の勉強に真剣に取り組み、それを通じて自己研鑽に対するモチベーションを高めることができました。
また、現在の仕事では、研究を進める中で壁にぶつかることが多くあります。しかし、大学・大学院時代の研究活動で培った「悪い結果も失敗と捉えない姿勢」を今も心がけています。研究はトライアンドエラーの連続なので、思い通りに進まないこともありますが、そのたびに落ち込むのではなく、次のステップにつなげることを意識しています。
学生時代、課外活動などは行っていましたか?

サッカー部のマネージャーをしていました。試合に勝ったときの選手のうれしそうな顔や、チームで喜びを分かち合えた瞬間は今でも忘れられません。
現役最後の大会の直前には、マネージャーたちで協力してCheer Up動画を作成しました。練習風景や試合のシーンを撮影し、音楽を付けて1本の動画にまとめました。新しい試みで時間もかかりましたが、チームのメンバーにも気持ちが伝わったようで、それを見たキャプテンから「勝つしかない!」という言葉をもらえたのがうれしかったです。
オフは週に1、2回で、それ以外は練習や試合が続きました。お盆休みの帰省も返上して活動することもありましたが、チームを支える役割としてやりがいを感じていました。
高校生や受験生に向けて、メッセージをお願いします!
YCUは小規模だからこそ、先生方やキャリア支援の方々との距離が近い環境があります。私自身、入学時は将来の道が見えず悩んでいましたが、多くの人の支えがあったおかげで自分と向き合い、研究者としての道を歩むことができました。
大学ではたくさんのチャンスがあります。その機会をぜひ自分のものにしてください!

