
損傷した神経回路がリハビリによって新しい機能を獲得し回復していく、神経の「可塑性」のメカニズムを研究し、リハビリ促進薬の開発に挑戦している阿部弘基准教授。さまざまな現象などから本質を引き出そうとする視点や、論理を美しいと思う感性が大切だと語る阿部准教授に、現在の研究内容から研究者を目指したきっかけなどを語ってもらいました。

神経回路のメカニズムを追究して
新しい診断や・治療の可能性に挑戦したい
現在の研究テーマについて教えてください。
脳卒中や脳梗塞による脳神経の損傷を対象に、リハビリによって脳内の神経回路の可塑性(経験や学習によって脳の神経回路が変化していくこと)が促進されるメカニズムについて研究しています。
病気や事故で神経回路が傷つけられると、手足の自由な動きが制限されることがあります。しかし、傷つくのを免れた神経回路が、リハビリによって壊れた回路に代わる迂回路として書き換えられ、再び手足を動かせるようになります。神経系には学習によって神経細胞同士の結合の強弱が変化する性質が備わっているためです。
ただし、必ずしもすべてのケースで手足が完全に回復するわけではありません。私はこの課題を解決するために、神経系に備わっている可塑性を高め、麻痺した手足を元通りに動かせるようにする「リハビリ促進薬」の研究を進めています。動物実験だけでなく、実際の麻痺の患者さんを対象とした臨床研究や治験に進めて、個々のリハビリによる回復力を高められる治療法の確立につなげたいと考えています。
現在の研究テーマを決めたきっかけがあれば教えてください。
YCU医学生時代、SF漫画の『攻殻機動隊』が好きで、「脳と精神・身体」に対する多面的な興味を持っていました。5年次に、病棟実習の帰りに金沢八景キャンパスの生協書店に寄って、たまたま手にした一冊の雑誌『現代思想』で「脳科学の最前線」が特集されていて、そこに掲載されていた哲学者・倫理学者の小泉義之先生の文章に感銘を受け、脳神経内科を専攻しようと決めました。以後は、脳神経内科疾患についてどのような研究をするべきか、を考えながら学んでいました。
研修医が終わる頃、高橋琢哉教授(生理学)から「可塑性を高める化合物を何に応用するか」という相談を受けて、「脳卒中後遺症のリハビリを促進できるのではないか」という議論に発展したことをきっかけに、医学部卒業後3年目から現在の研究テーマに取り組むことになりました。
リハビリテーション医療はまさに個別医療の代表格であり、患者さんの障害の程度や生活目標、仕事内容に合わせたリハビリが行われています。しかし、生物学的な原理に基づく回復プロセスがあるはずなので、その理解を深め、薬で回復をサポートすることで、個別の回復を促進する医学の可能性に挑戦しています。
研究者を志した理由やきっかけなどを教えてください。
中学生の頃、数学や物理学に興味を持ったことをきっかけに、一般向けの科学書や科学雑誌を読む日々の中で、将来は研究職に就きたいと夢見ていました。一方、公務員の父の影響で「社会のために、人のために」という信念が自分の人生観の根幹にあったので、医学を志すことは自然だったような気がします。ただ、生来のあまのじゃく気質もあり、医学への歩みはスムーズではなかったものの、映画や小説、音楽に浸るモラトリアム期間(医学部入学以前に他大学在籍)を経てYCUの医学部に入学しました。
入学後も、映画を見たり本を読んだりとのんびり過ごしていました。しかし、4年次に、当時赴任されたばかりの高橋教授(生理学)のリサーチクラークシップ(基礎研究あるいは臨床研究を各研究室で学ぶ制度)に参加、そこで神経可塑性という概念に興味を抱き、かつて思い描いていた研究職への志望を再確認しました。
研究の面白さや醍醐味などについて教えてください。
現在、私が進めているリハビリ促進薬の研究開発は、効果のある薬を世の中に送り出すことを目的としているだけでなく、神経可塑性が医学的に有用な概念であることを証明していく試みでもあります。単に生物学的に面白い現象を追求するだけでなく、その現象を臨床研究や治験を通じて実際の治療や診断にどう役立てていくのかを考えるのは、医学部ならではの研究であり醍醐味です。
そして研究手法が多岐にわたることも魅力的で、動物の行動実験からヒト脳画像解析まで幅広く経験することができます。また、YCUだけでなく、さまざまな大学・病院・研究所・製薬企業の方々との協働を通じて自分自身の視野を広げることができ、これによりますます研究への情熱が湧いています。
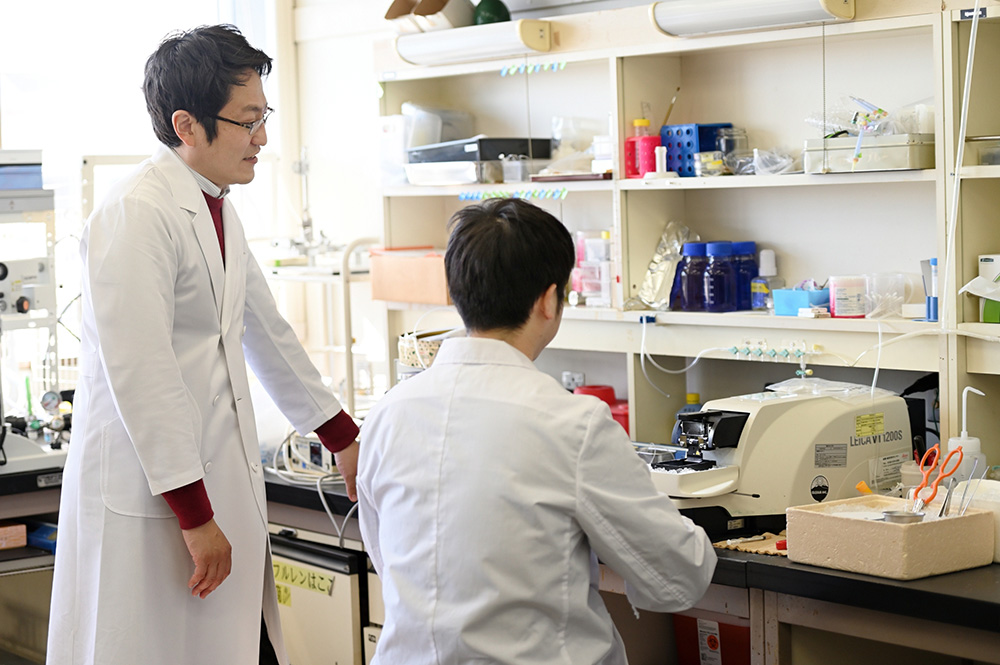
日頃は基礎医学研究者でありながら、脳神経内科で外来診療にも携わっていらっしゃいますね。その理由を教えてください。
神奈川県内の病院で脳神経内科専門医として、週1回外来診療を行っています。その理由は、研究だけでなく臨床の現場に触れる必要性を感じているからです。医学研究を発展させていく上で大切なことは、机上だけの学びにとどまらず、実際の診療現場から学び多面的な発想を身に付けることだと思います。地域医療では、患者さんの話をしっかり聞き、相手の立場に立ち、生活を支えることが重要であり、都市部の医療機関とは異なるスキルが求められます。先進的な技術よりも、患者さんの実際の生活状況を理解し、医学的な知識を駆使してサポートすることが重要とされています。
このような地域における診療と研究は決してかけ離れているわけではありません。特に神経疾患はアルツハイマー病に代表されるように解決すべき有病率の高い病気に、地域医療の場で多く遭遇します。つまり、最前線での医療が最先端の研究の芽を育む場であり、課題や方向性を見出すことのできる貴重な機会であると感じています。医学は幅広い知見が必要とされます。また、地域の生活の基盤的な側面にも興味を持つことが医学研究の方向性を見失わないためには重要だと考えます。
研究者にとって一番必要な素養(能力)は何でしょうか。
私は生理学教室で研究しています。生理学は生物学的な原理を見出すための学問であり、事実の蓄積から現象のエッセンスを引き出す力が求められる領域です。さまざまな現象や物質の関係性の中から生物学的な原理を見出す必要がある学問なので、「本質」だけを引き出そうとする「ミニマリスト的感性」を磨くようにしています。そのためには、「論理を美しい」と思える感性も必要だと考えます。真面目であることよりも熱心であること、試験勉強が得意であることより(頭の回転がはやいことより)も研究の動機が明確であることが大切と感じています。
学生たちが研究を進めていくうえで、心がけてほしいことを教えてください。
「なぜこの研究を進めたいのか」「なぜこの現象に関心があるのか」という研究の動機を素直に自分の言葉で語れることが、心のこもった良い研究をする上では重要な要素だと考えます。動機が明確であれば、研究の日々が高揚感に満ちたものになると思います。そして、研究者は「researchers' high」の状態にある人と語り合える時間を共有できることに喜びを感じるものです。
そのためには、学部学生も大学院生も積極的に教科書や論文を読み、あるいは病気の本質を捉えるために患者さんの症状に熱心に向き合い見極めて、仲間や教員とよく議論してほしいと思います。
YCU受験生へのメッセージをお願いします。
医学部での学びは可能性を広げます。入学後は「臨床医ありき」で進路を考えるのではなく、自分の心に素直に従い学びたいことを学んで、自由に、そして柔軟に医学の世界を飛び回ってください。
受験勉強は、大学での学びに必要な能力や姿勢を最適化する素晴らしい機会です。数学や英語などどの科目においても、何を問われているのかを理解する力と、その背景に思いを致す感性を磨くことが大切です。これは将来、医師として働く際に患者さんとのコミュニケーションにおいても役立つアプローチです。
大きな空が広がる海辺の福浦キャンパスで、さまざまな可能性に満ちた皆さんとお会いできる日を心から楽しみにしています。


「ヨコ知リ!」アンケート(締め切りました)
ご回答いただいた方の中から抽選でYCUオリジナルグッズをプレゼント! 当選者の発表はグッズの発送をもって代えさせていただきます。
※グッズの指定はできません。
(2024/07/04)
