難聴・人工内耳診療のご案内
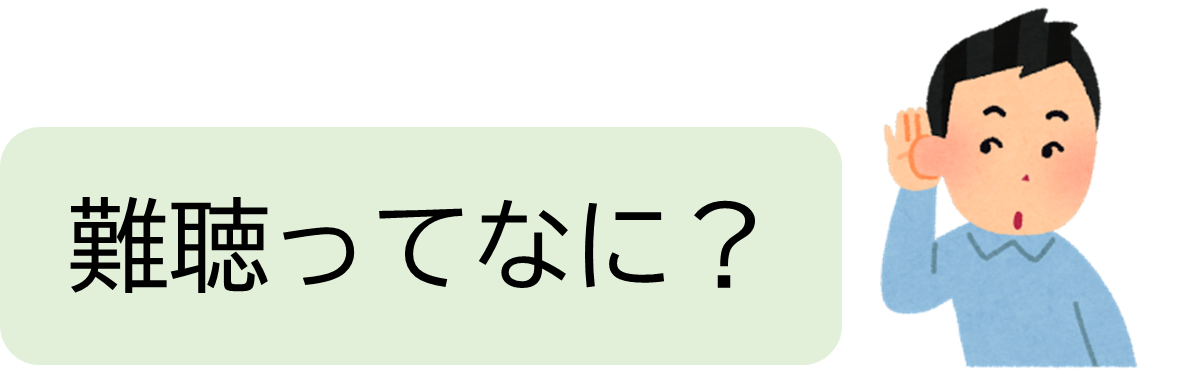
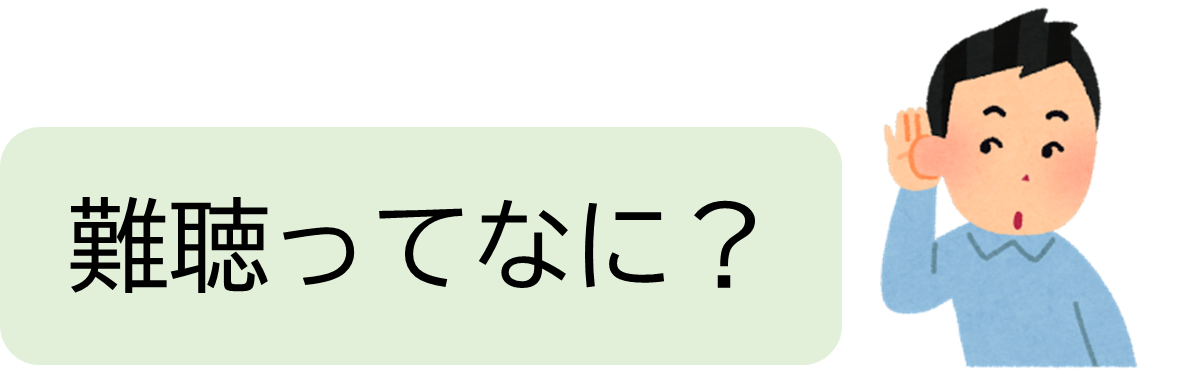
難聴とは、音や言葉を聴く能力が低下している状態です。全く聞こえない状態から少し聞こえる状態まで種類や程度はさまざまです。成人の場合、難聴を放置していると、将来的に認知症となるリスクが高まる等、QOL(生活の質)に大きくかかわります。
小児について、約1000人に1人、先天性難聴のお子さんが生まれます。難聴児の多くは聴こえるご両親から生まれます。近年は新生児聴覚スクリーニング検査の普及により、より早期に難聴が発見されるようになりました。難聴があると、言語の習得、コミュニケーション能力・社会性の発達などさまざまなことに影響します。そのため、なるべく早期に補聴器や人工内耳を使用して聴覚を補い、適切な療育を行うことが大切です。
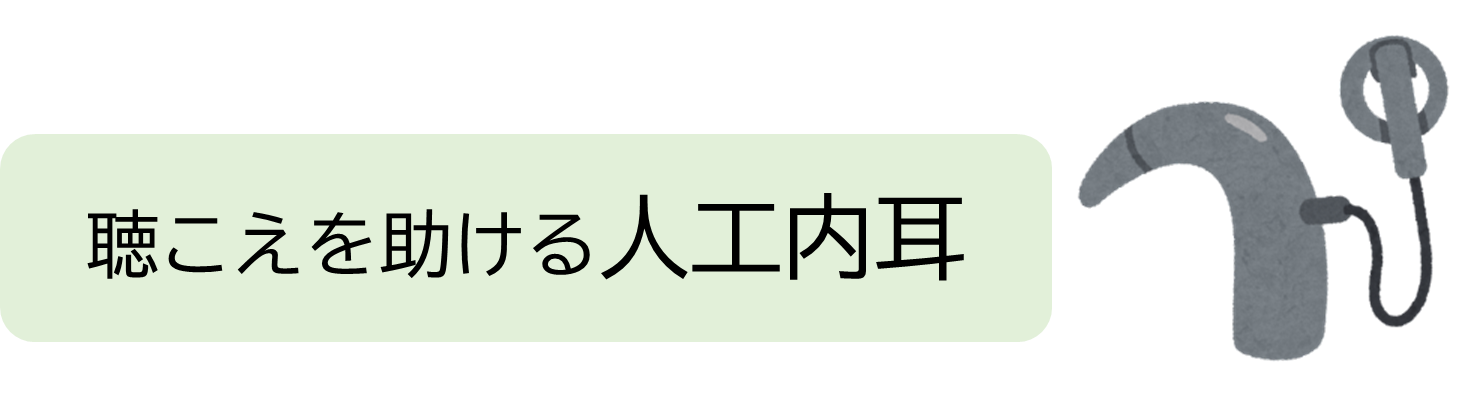
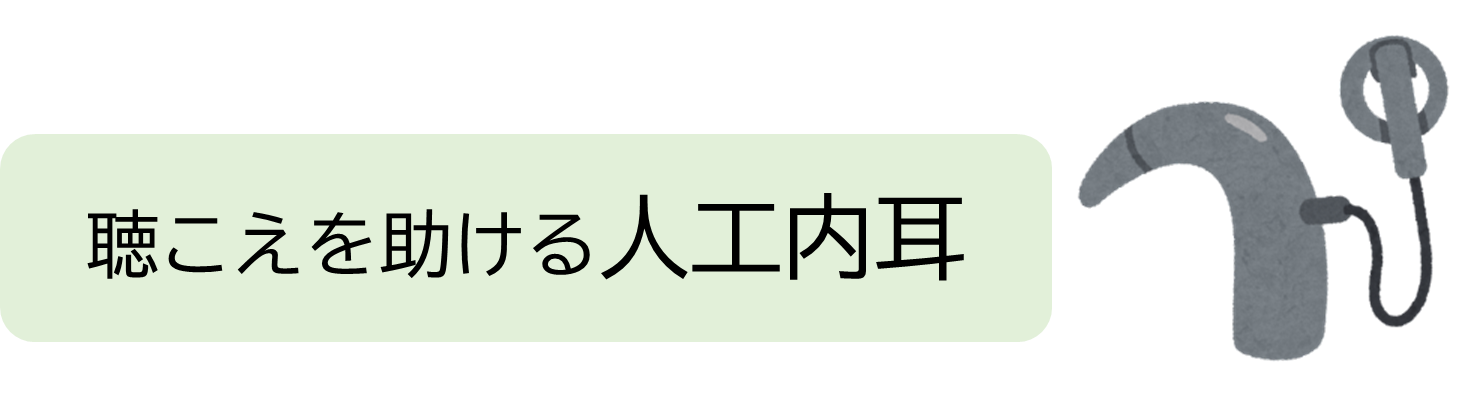
高度・重度感音難聴の方の聴覚補償の手段のひとつとして、人工内耳を用いることがあります。人工内耳とは、手術で内耳に電極を埋め込み、神経に直接電気刺激を与えて音を聞かせる人工臓器です。
日本では現在、年間約1000件の手術が行われています。小児の場合、手術が可能になるのはおおむね1歳からです。成人の場合、先天性難聴の方や、病気等で中途失聴となった方にも手術が適応となります。人工内耳は補聴器に比べて、低音から高音までより小さな音も入力することができます。しかし効果には個人差があり、術後の調整およびリハビリ・療育が重要となります。
当科では、2000年から人工内耳診療を開始し、現在まで約200例の手術とリハビリを実施しています。
「人工内耳/難聴外外来」「補聴器外来」のご案内
| 人工内耳/難聴外来 補聴器外来 |
|
第1・3水曜日(祝日除く) 14時~16時 |
|---|---|---|
| 言語聴覚士による 聴こえとことばの訓練 |
月曜日~金曜日(祝日除く) 9時~17時 |
|
| 一般外来 | 月曜日~金曜日(祝日除く) 9時~12時(受付10時30分まで) |
|
- 初診の場合は、まず一般外来に受診していただく必要があります
- 病院HPにて初診紹介予約をしてください
- 初診時には紹介状(診療情報提供書)をご持参ください
初診予約の方法
患者さん・ご家族から 医療機関から
難聴に関する遺伝子検査
先天性感音難聴の約6割は遺伝子変異が原因だといわれており、また原因遺伝子が判明すると、難聴の程度や予後、もしくは難聴以外の症状が出現するかどうかが分かることがあり、今後の治療に役立てることが期待されます。当科にて遺伝子検査が可能であり、検査費用には健康保険が適用されます。
聴覚検査について
難聴の程度や原因を判断するためには聴覚検査が必要となります。当院では、一般的な聴力検査の他に、耳音響放射(OAE)、聴性脳幹反応(ABR)、聴性定常反応(ASSR)といった検査により、より詳細に聴覚について調べることが可能です。
当院は精密聴力検査機関です。新生児聴覚スクリーニング検査でリファー(要再検)となった場合も受診いただけます。
当院は精密聴力検査機関です。新生児聴覚スクリーニング検査でリファー(要再検)となった場合も受診いただけます。
補聴器について
難聴がある場合はなるべく早期に補聴器を装用し、できるだけ聴覚を活用することが大切です。当科では補聴器専門店と協力し、補聴器が必要だと診断された直後から補聴器の装用をスタートできるよう言語聴覚士がサポートします。
難聴・人工内耳診療の流れ
-
1
診察
各種検査(聴覚検査、CT検査、遺伝子検査など)
-
2
調整・訓練
小児
補聴器導入・調整
療育施設への紹介
定期診察成人
補聴器店への紹介・調整
定期診察
言語聴覚士による人工内耳療法の特徴
高い専門性
当院には、聴覚検査や補聴器の調整、人工内耳患者の訓練を行う聴覚専門の資格を持った言語聴覚士※がいます。補聴器・人工内耳、お子さんの療育に関する相談にも対応しますのでお気軽にお声がけください。
※認定言語聴覚士(聴覚障害領域)
※認定言語聴覚士(聴覚障害領域)
術前から長期にわたるフォロー
人工内耳のご希望があり手術適応となっても、手術の前に人工内耳についてよく理解された上で手術をしていただくことが重要です。術前から言語聴覚士が時間をかけて詳しく説明し患者様の疑問や不安にもお答えします。術後、調整や聴こえが安定しても、半年~1年に1回は人工内耳の状態確認や調整で通っていただいております。
頻回な調整・訓練
成人の人工内耳について、人工内耳を装用しただけでは十分な効果を発揮できないため、頻回な調整と訓練が必要となります。当院では、音入れ後から調整が安定するまでは週1回通っていただいております。また、聴こえの成績が向上している間は、頻回に訓練・評価も行っていきます。さらに、自宅での訓練についても提案します。
充実の療育
お子さんは人工内耳を装用しただけでは聴こえやことばは十分に発達せず、良好な発達のためには的確な働きかけが必要となります。そのため、当科では人工内耳を装用されたお子さんを対象に、聴こえとことばの訓練を就学前まで週1回1時間行っています。また定期的に評価した後、現在の状況、今後の方針や現在必要な働きかけについて具体的に保護者へ説明し、ご同意いただいた上で進めていきます。


他施設との連携
人工内耳装用のお子さんが通う、ろう学校、地域の保育園・幼稚園、療育センターと連携し対応しています。当科の言語聴覚士がお子さんの通われている各施設に赴き、人工内耳の機器についてやお子さんの現在の聴こえ・ことばの発達と必要な働きかけについて説明・共有しています。お子さんが通われている施設と連携して療育を進めていきます。
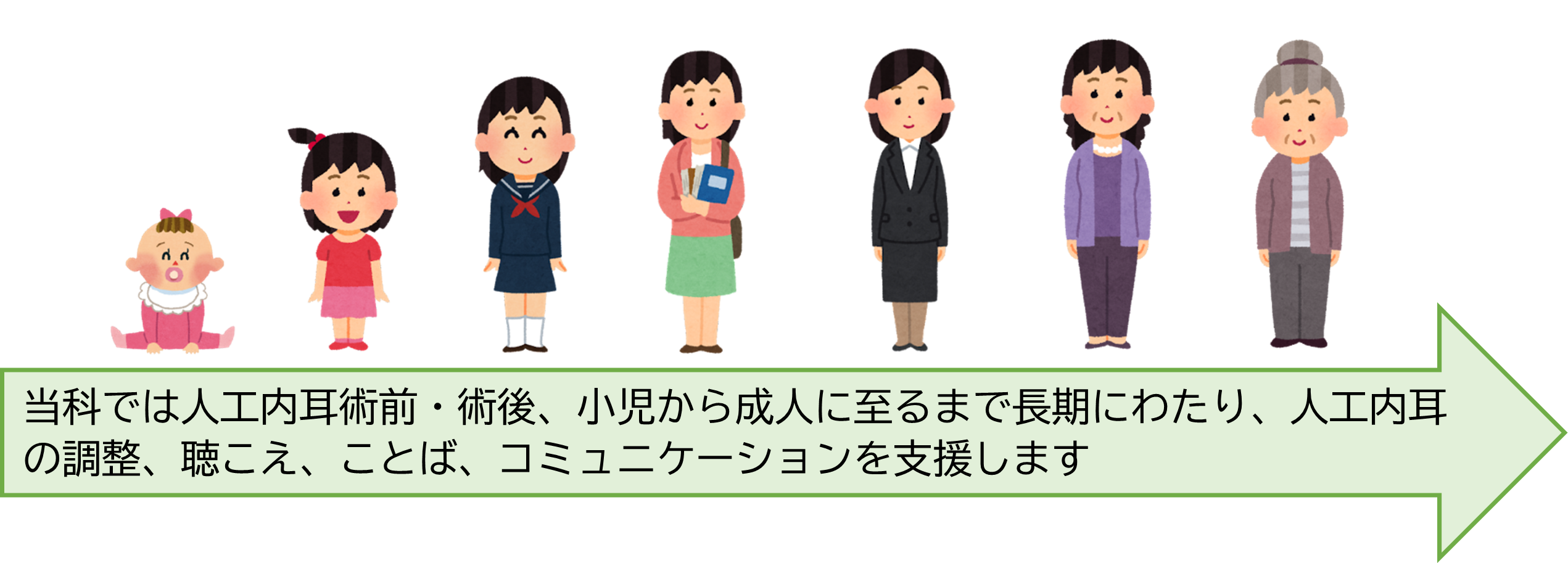
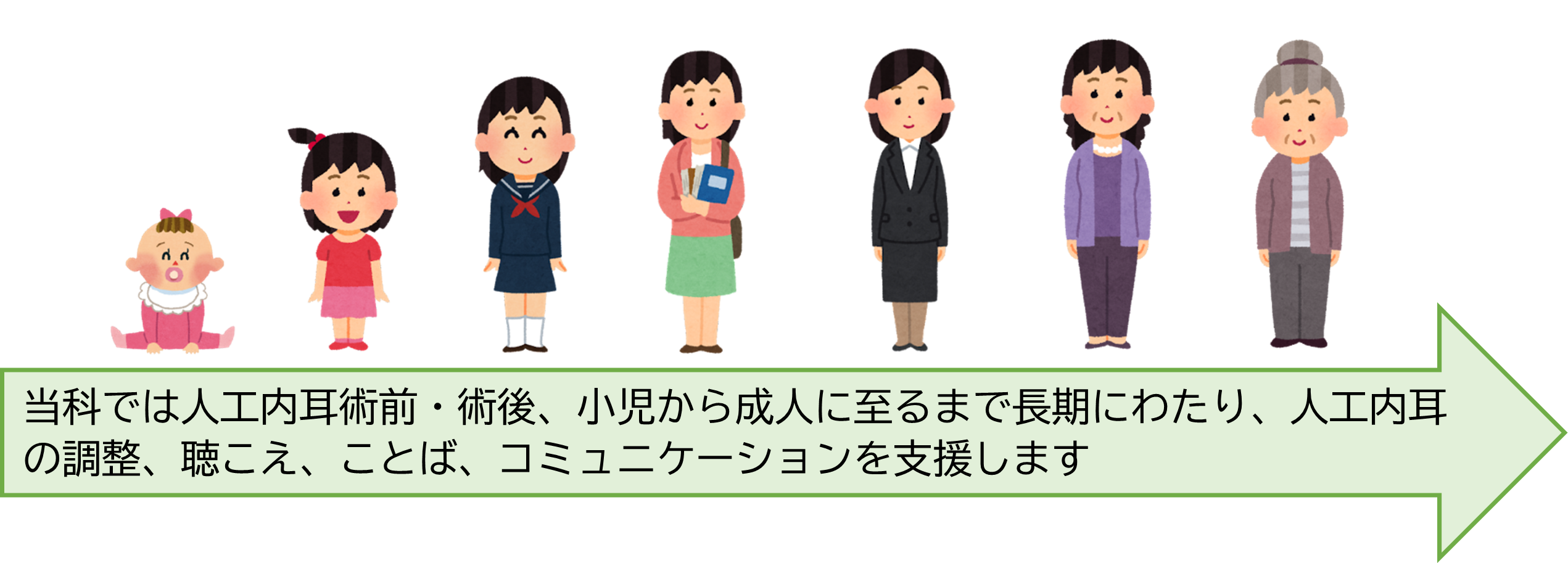
人工内耳診療・訓練について よくあるご質問Q&A
幼少期には、十分な働きかけが必要であり、着実な発達を促すためには頻回な週1回の訓練が必要であると考えています。しかし、ご家庭のご都合等でなかなか通うことができない場合は、ご相談の上で対応いたします。
訓練の効果が見込まれる場合は、就学後も訓練の継続が可能です。頻度は月2~3回程度となります。
人工内耳装用から長期間経過しても、定期的な機器の確認や調整が必要です。そのため、特別なご事情がない場合は、年に1回は必ず通院していただいております。
可能です。当院のホームページにて初診紹介予約をしてください。受診の際、紹介状の他にCT等の画像データとマップデータをご持参ください。

