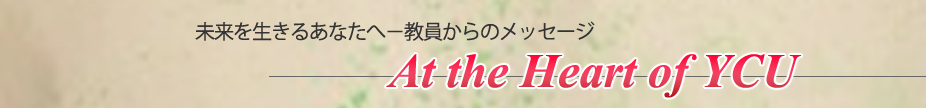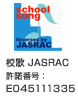HOME > 教員からのメッセージ − At the Heart of YCU > 人間の精子形成を体外で成功させるための研究を行っています - 小川毅彦准教授
人間の精子形成を体外で成功させるための研究を行っています - 小川毅彦准教授
培養下での精子形成に関する研究が科学雑誌「Nature」に掲載
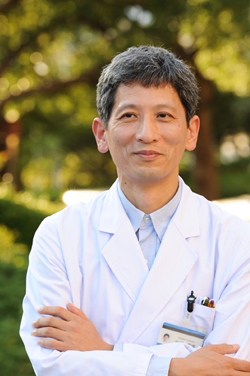
私たちが取り組んでいる研究は、「培養下での精子形成法の開発」です。つまり、通常は体内の精巣の中でつくられている精子を、体外でつくり出そうという取り組みです。
精子の元になる精子幹細胞を体内から取り出し、培養皿の上で体内と同じような環境を与えることによって、幹細胞から細胞が分裂し、精子になるまで培養していきます。精子が形成される期間はマウスだと35日必要ですが、全工程を培養下でつくり出すことに、昨年世界で初めて成功することができました。
この研究をまとめた論文が、イギリスの専門雑誌「Nature」に掲載されました。自分たちの研究が世界的に脚光を浴びたことは、素直にうれしかったですね。
|
小川 毅彦(おがわ・たけひこ) 医学群 准教授 (学部)医学部 附属病院 培養下での精子形成と体外受精の成功は、不妊治療への応用が期待され、注目を浴びている。来年度からは、新設の生命医科学研究科の学生を指導するとともに、附属病院での診療も続ける予定。 |
不妊症マウスの正常な精子形成にも成功
次に、私たちは精子形成を体内でうまく行えないマウス使って、実験を行いました。先ほどの実験と同様に、マウスから精子幹細胞を取り出し、精子形成が行えるように整えた環境下で培養した精子を、体外受精によって交配し実際に子どもが生まれたのです。
この研究は、科学雑誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載されました。動物での事例ではありますが、体外精子形成により次世代へ命をつなげることを証明でき、不妊治療に悩む人にも応用できる可能性を示すことができました。
子孫への遺伝子伝達能と多能性を備えた生殖細胞の魅力に惹かれて追究
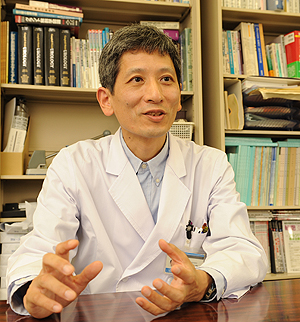
精子や卵子になる生殖細胞には、泌尿器科に入局した当初から興味を持っていました。当時読んだリチャード・ドーキンス著の「利己的な遺伝子」という本に書かれていた“個体は遺伝子の乗り物に過ぎない。遺伝子だけが、世代を超えて生き延びるのだ”という発想が、自分の中で印象に残っていたのです。
たしかに生殖細胞にある遺伝子だけが次世代に伝わることができます。種としてみたときに、生殖細胞以上に重要なものはないと思っていたわけです。当時、医学界でも生殖細胞を研究する人は少数派で、さらに泌尿器科の中でも前立腺がん、腎臓がんなどの研究を志す人が多かったこともあり、自分がやるしかないという使命感もありました。
生殖細胞には次世代に伝える遺伝子を内包しているだけでなく、多能性という特徴を持っています。多能性というのは、血液や筋肉、神経などのさまざまな細胞になることのできる力です。その特徴を持つ細胞は、体のなかで精巣と卵巣しかないといわれています。
当時は、その多能性というのは何なのだろうかと純粋に興味を抱いていました。その後、生殖細胞を用いて腎臓をつくりたいとも考えるようになりましたね。
誰も考えたことのない分野に挑戦することが研究の醍醐味
研究者としてのゴールはヒトの精子形成

「培養下での精子形成」の研究に明確な目標を置いたのは、2007年頃です。研究者として残された時間を考えたときに、自分のキャリアの中で明確な目標を持ちたかったのです。2010年にマウスでの実験においてはすでに成功しましたが、ヒトの精子を培養下でつくることが、自分の研究者としての一つのゴールだと思っています。
培養下でヒトの精子形成ができれば、あとは次の世代がさらに可能性を広げてくれる。不妊治療をはじめ、さまざまな臨床実験も可能になります。その土台をつくりたいですね。
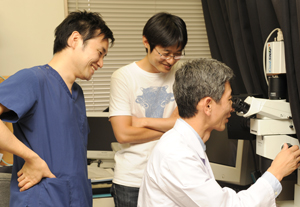
欲ばりとは思いますが、新たな研究でもう一度「Nature」に掲載されてみたいという個人的な希望もあります。実は現在、生体から採取した組織片を体外で生かす期間を、人間の寿命ほどの長さまで延長できないかとも考えています。精子形成の研究を行っているなかで、どうして体外では組織片は数日でダメになってしまうのか、ということに疑問を抱きました。最も良い培養条件でも2ヶ月ほどしか維持できません。しかし、体外でも、体内と同じ環境を与えることができれば、それは不可能ではないはずです。
半導体の技術で、細い流路を作り培養液を流して模擬生体を作ることができると聞いたことがあります。可能性は未知数ですが、誰も考えたことがない分野に挑戦することが研究の魅力だとも思います。
来年度から生命医科学研究科の担当(※)にもなります。学生たちと互いにアイデアを出し合いながら研究を進めてゆくことはとても楽しいと思います。そして、彼らに研究のバトンを渡していきたいと思っています。
※国際総合科学部2012年入学生からは理学系に「生命医科学コース」が新設されたが、このコースの学部生も指導を行う。
(2012.10.29掲載)