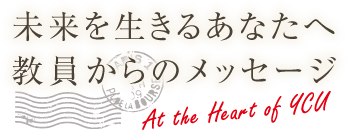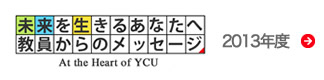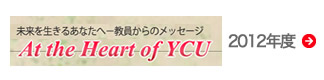臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」
その実現のために研究に取り組んでいます
医学群 臓器再生医学 准教授
武部貴則
たけべ・たかのり

再生医療の可能性を追い求めて
臓器の原基(種)を創るという発想
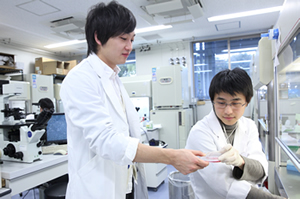
私が再生医学の研究を始めた4年前、研究の現場ではiPS細胞[keyword2]などの万能細胞を用い、臓器の機能を担っている細胞を人工的に創り出す手法がとられていました。つまり臓器そのものではなく、目的とする機能を担う1種類の細胞を創出し、そのレシピを開発するというものでした。しかしこれでは、私が目指した臓器移植の代わりになる医療として十分な役割を果たすことはできません。実際に、その細胞を使った治療と臓器移植を比べると、明らかに臓器移植の方が成功率が高いという結果が出ていました。そこで私は、「臓器そのものを創る」という目標を掲げ、そのためのアプローチを考え始めたのです。
「臓器を創る」と言っても、臓器の内側には多種多様な細胞が秩序立って配置されているため、これをすべて人間の手で再現するのは現実的ではありません。そこで私は、「胎児の臓器のように初期的な構造であれば、比較的簡単に創れるのではないか」と考えました。この発想から、私たちは肝臓の原基(種)を創り出し、2013年には、原基からヒト血管構造を持つ機能的な肝臓に成長し、最終的に治療効果が発揮されることを明らかにしました。この成果は英国科学誌「Nature」に掲載されるなど、大きく注目されました。
私たちが「肝臓の種」と呼ぶこの原基は、文字通り植物の種と同じ意味を持ちます。植物の種は、土にまくとやがて芽を出し、実を付けるまでに成長します。これと同じように、肝臓の種を生体内に移植すると、自律的にヒト血管網を持つ機能的な肝臓へと成長するのです。
偶然の産物から気付いた、細胞の培養環境
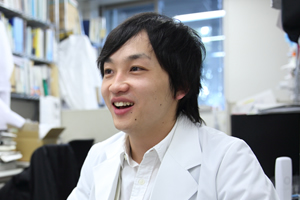
細胞には血管や軟骨など、それぞれの組織を形成することを目的とする細胞があります。私は肝臓の種を創出するため、肝臓の機能を創る細胞のほかに、血管の細胞とそれらを繋ぐ指示を行うサポーター役となるような細胞を混ぜることを試みました。この手法は従来のように一つ一つの細胞を創っていた研究とは全く反対の発想で、画期的な試みではありましたが、当初は「余った細胞がもったいないから混ぜてみよう」くらいの気持ちで始めたのです。
ところがその翌日、細胞を混ぜておいた培養皿に、モコモコした立体の組織ができていたのです。通常、細胞を培養する際は、肉眼で見えるような明らかな反応はなく、顕微鏡でやっと確認できる程度のものしかありません。これを見た私は一気に気持ちが高揚しました。「これは臓器ができる最初の現象に違いない」と思った私は、研究室の複数のメンバーに見せたところ、初めはほとんどの人が半信半疑で、「カビではないか?」と言った人もいましたが、確信を持っていた私は、さらに実験を続け、実際に立体組織を形成していることを立証したのです。
この発見には、ある偶然も味方になってくれました。それは培養に使った器具です。通常、細胞の培養に使う培養皿は、細胞を密着させるためのコーティングが施されたものを使います。この時、私が使った培養皿は、たまたまコーティングが施されていないものだったのです。そのため、細胞が自発的に動き、立体組織が形成されたのです。この偶然によって、これまで常識と考えられていたことが覆され、細胞が自由に動くことができる新たな培養環境に気付くことができました。この経験がなければ、未だにそのことに気付いていないかもしれません。
Keyword 2iPS細胞
皮膚などの細胞に特定の遺伝子を入れることで、心臓や肝臓、神経などの細胞になる能力を持つ人工多能性幹細胞。培養して人工的に増やすことができ、再生医療や創薬研究など、幅広い分野での応用が期待されている。この細胞の生成に成功した功績により、京都大学の山中伸弥教授が2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。
-
vol.08
臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」その実現のために研究に取り組んでいます

医学群
臓器再生医学 准教授武部貴則
-
vol.07
臨床の現場や子育て支援に役立つ心理学の研究を目指したい

国際総合科学群
臨床心理学 准教授平井美佳
-
vol.06
有機合成化学の力で未来を切り拓く有用なものを作り出したい

国際総合科学群
天然物有機化学 准教授石川裕一
-
vol.05
患者さんのために科学的根拠のある看護ケアの研究を深めたい この思いは世界へと続きます

医学群
看護生命科学 教授赤瀬智子
-
vol.04
進化する医療技術を駆使し、婦人科がんの治療に挑んでいます

医学群
がん総合医科学 教授宮城悦子
-
vol.03
人々が生き生きと暮らす現代のニーズに合ったまちづくりを考える

国際総合科学群
都市計画論 准教授中西正彦
-
vol.02
データを重視した研究で、世の中のできごとの本質を見極める

国際総合科学群
税務会計論 准教授高橋隆幸
-
vol.01
難病の原因を解明し、病気に苦しむ子どもたちを笑顔にしたい

医学群 小児科学(発生成育小児医療学)教授
伊藤秀一