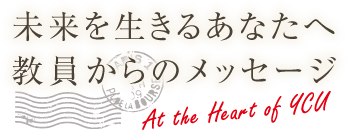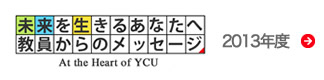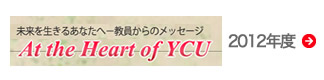有機合成化学の力で未来を切り拓く
有用なものを作り出したい
国際総合科学群 天然物有機化学 准教授
石川裕一
いしかわ・ゆういち
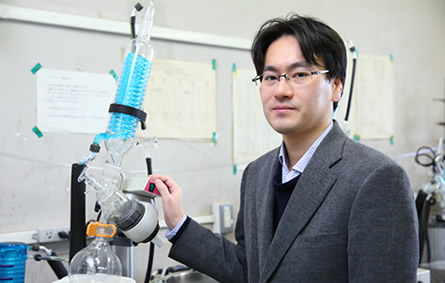
苦労の末に生まれた研究成果
研究は常にトライ&エラーの繰り返し
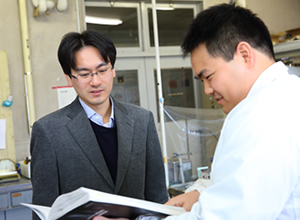
研究対象となる物質については、他の研究者の論文の中から探すこともあります。例えば「がんに効きそう」「インフルエンザに効きそう」といった情報を見つけ出し、その中から興味を持ったものを研究しています。そして、物質の合成方法を有機化学の知識や経験から考えだし、何度もトライ&エラーを繰り返していきます。
成果を出すことができた思い出深い物質の一つに「ブリオスタチン」という化合物があります。ブリオスタチンは、海洋動物の「フサコケムシ」を研究材料として取り出されたもので、がんに効く作用を持っていました。これも、採取が難しいので研究にチャレンジしたわけですが、ブリオスタチンのような成功例はめったに出てきません。一つ一つの反応がうまくいかないのは日常茶飯事で、100回実験して1、2回うまくいけば良い方でしょう。
このように、日々トライ&エラーを繰り返して、中には全て無駄になってしまうような実験もあります。例えばある化合物は、その構造が論文に書かれていたので、その通りに作ろうとしましたが作れませんでした。構造が間違っていたのです。このように、存在しない形を作ろうとして失敗するというようなこともありました。
薬の開発につながった有機合成化学の研究

有機合成化学の研究分野において、最近のトピックスとなったものに「ハリコンドリンB」という化合物があります。現在、製薬会社のエーザイ株式会社から新しい抗がん剤「エリブリン」が販売されていますが、このもとになっているものが、神奈川県の三浦海岸などの磯で採れた海綿動物[keyword2]の「クロイソカイメン」に含まれる天然物のハリコンドリンBです。
人工的な合成が可能になったことで、ハリコンドリンBの構造を単純化する研究が進み、エリブリンの開発につながったのですが、このように自然から採れる物質から薬になるのはあまりないことなので、画期的なことと言えます。
ハリコンドリンBのように物質そのものが薬のもととして活用できるものもあれば、似たような形のものを作り出すことで薬の開発につながるものもあります。例えば、抗インフルエンザ薬は、ウイルスが体内で増殖する際に必要な酵素に働く物質に似せた形のものを作って開発しています。この酵素に働く物質は、シアル酸という化合物で、シアル酸の構造に似せた化合物をたくさん作っていくうちに、シアル酸と同様の働きをもつものが作られたわけです。
Keyword 2海綿動物
主に海に生息し、壺状、扇状、杯状など、さまざまな形態をもつ海の生物。筋肉や神経、感覚細胞はもたず、多細胞動物の中では最下等に位置する原始的な動物群。-
vol.08
臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」その実現のために研究に取り組んでいます

医学群
臓器再生医学 准教授武部貴則
-
vol.07
臨床の現場や子育て支援に役立つ心理学の研究を目指したい

国際総合科学群
臨床心理学 准教授平井美佳
-
vol.06
有機合成化学の力で未来を切り拓く有用なものを作り出したい

国際総合科学群
天然物有機化学 准教授石川裕一
-
vol.05
患者さんのために科学的根拠のある看護ケアの研究を深めたい この思いは世界へと続きます

医学群
看護生命科学 教授赤瀬智子
-
vol.04
進化する医療技術を駆使し、婦人科がんの治療に挑んでいます

医学群
がん総合医科学 教授宮城悦子
-
vol.03
人々が生き生きと暮らす現代のニーズに合ったまちづくりを考える

国際総合科学群
都市計画論 准教授中西正彦
-
vol.02
データを重視した研究で、世の中のできごとの本質を見極める

国際総合科学群
税務会計論 准教授高橋隆幸
-
vol.01
難病の原因を解明し、病気に苦しむ子どもたちを笑顔にしたい

医学群 小児科学(発生成育小児医療学)教授
伊藤秀一