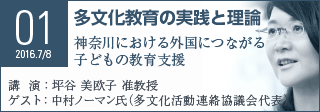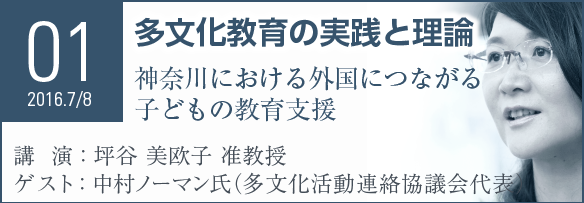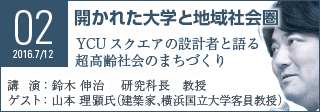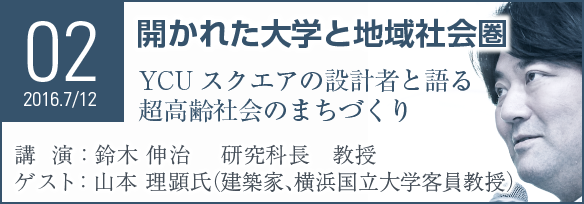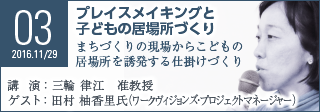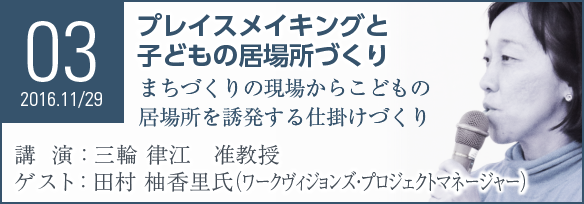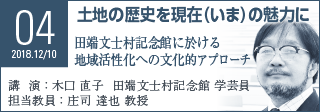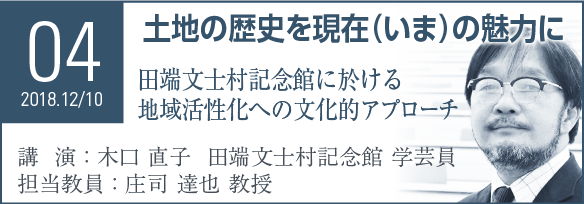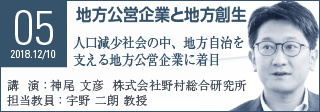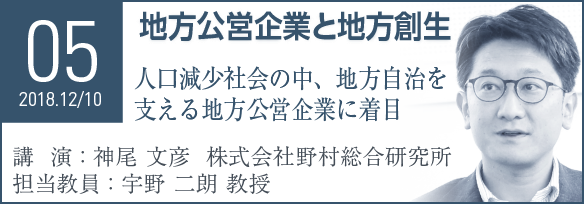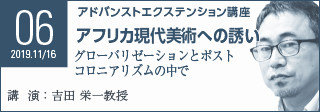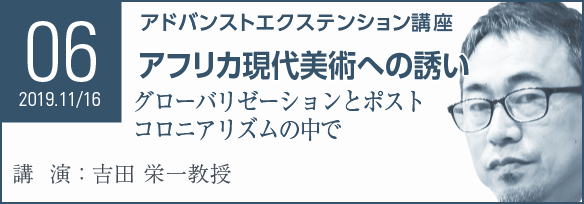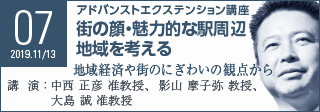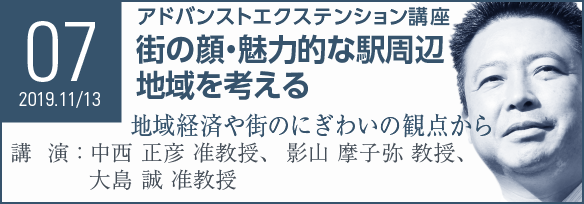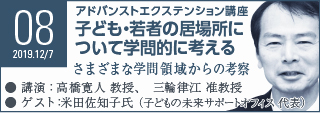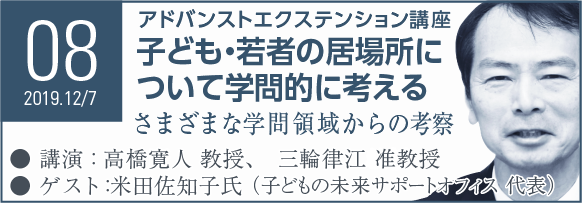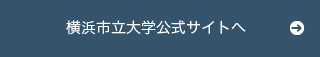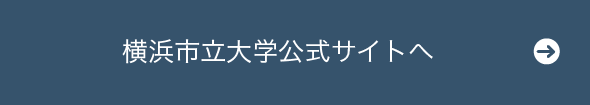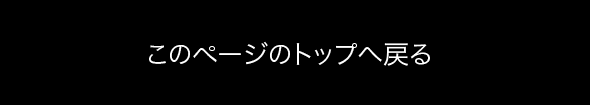研究セミナー特集
 多文化教育の実践と理論
神奈川における外国につながる子どもの教育支援
多文化教育の実践と理論
神奈川における外国につながる子どもの教育支援
開催日 / 2016年7月8日(金) pm6:00〜7:30
開催場所 / 横浜コミュニティデザイン・ラボ さくらworksイベントスペース(横浜市中区)
講演 / 坪谷 美欧子 准教授
ゲスト / 中村ノーマン氏(多文化活動連絡協議会代表)
発表/院生 中沢英利子さん
2. 講師 坪谷 美欧子 准教授による講演

Mioko Tsuboya坪谷 美欧子 准教授

横浜市立大学 国際総合科学群 人文社会科学系列
国際総合科学部 国際教養学系 国際文化コース
大学院 都市社会文化研究科 都市社会文化専攻
准教授
立教大学大学院 社会学研究科 博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員、横浜市立大学 商学部経済学科講師を経て現職。
2011年より川崎市人権施策推進協議会、多文化共生社会推進指針に関する部会委員、2015年よりかながわ国際政策推進懇話会委員を務める。
国際化に伴い、日本にも海外からの流入者が増えたことで、外国につながる子ども達がさまざまな課題を抱えていることに早くから着目。これを社会学の観点から考察し、現代社会が解決すべき課題であるとして研究を重ね、本学大学院では社会文化論特講を担当。学生を導くとともに、県内の高等学校で、外国につながりのある生徒への支援活動に関わる等、行動力と発信力を兼ね備えた活動を行っている。
アメリカの歴史に見る「多文化教育」の起源
坪谷でございます。
私は横浜市立大学大学院で、エスニシティ文化論(※)という科目名で大学院生とともに「多文化教育」の理論を整理しながら、欧米、日本など先進国で外国につながる子どもたちや移民に関する政策にどのような意味合いがあるのかということを研究しています。今日の発表はそうした大学院生とのディスカッションの中で浮き彫りにされた問題などにもフォーカスして、お話をしていこうかと思っています。
まず、今回の研究セミナーのテーマでもあります、「多文化教育」という概念はアメリカではじまった学校の改革運動、教育の改革運動に起因するもので、非常に実践的な意味合いを持って捉えられて来たというところが、特徴的なのではないかなと思います。
ご存知の通り、アメリカは移民の国でありながら、建国以来、白人の人たちが政治、経済、社会システムの中心にありまして、1960年代の半ばまでは、黒人や非白人の人たちの歴史や文化については、教科書でもほとんど触れられてこなかったという事実があります。それが1950年頃から始まった黒人の人たちによる人権運動が広まり、ケネディ大統領の跡を継いだリンドン・ジョンソン大統領のもとで1963年に公民権法が成立しました。ようやく、 いわゆるマイノリティとされる人々の権利を保障していこうということになったわけです。これによって、大きく変化したのが高等教育の現場です。例えばエスニックマイノリティーの人たちが優先的に大学に入れる制度が設けられたり、それに伴って企業でもマイノリティの人たちを受け入れる枠ができるなど、教育の変化が社会に大きなインパクトを与えました。こうした高等教育機関の変化がやがて初等教育、中等教育にも波及し、全体として「多文化教育」につながる教育改革運動が一応の成果を見せたと解釈できます。多文化教育理論で有名な、ジェームズ・A・バンクスという学者も、「多文化教育」の起源は、アメリカの公民権運動であると定義しています。
いわゆるマイノリティとされる人々の権利を保障していこうということになったわけです。これによって、大きく変化したのが高等教育の現場です。例えばエスニックマイノリティーの人たちが優先的に大学に入れる制度が設けられたり、それに伴って企業でもマイノリティの人たちを受け入れる枠ができるなど、教育の変化が社会に大きなインパクトを与えました。こうした高等教育機関の変化がやがて初等教育、中等教育にも波及し、全体として「多文化教育」につながる教育改革運動が一応の成果を見せたと解釈できます。多文化教育理論で有名な、ジェームズ・A・バンクスという学者も、「多文化教育」の起源は、アメリカの公民権運動であると定義しています。
とはいえ、当初の「多文化教育」は、異なる文化的背景を持つ者への教育で、マイノリティの人たちをマジョリティの人たちの社会へ適応させるためといった側面がありました。しかし、子ども達が一緒に勉強する環境においては、マジョリティーの側もより沿っていかないとコミュニケーションが成り立ちません。そうしたことから徐々に相手の歴史や文化を再評価するという動きが出てきて、現在のアメリカの「多文化教育」が成熟してきたと考えられます。こうした動きがやはり移民を抱えるヨーロッパにも影響を与え、この分野に関しては、欧米がやはり一歩進んでいると評価できるかと思います。
今日アメリカで行われている「多文化教育」が、そのまま日本で受け入れられるかというと、これは難しい問題があると思うのですが、先ほど、中村ノーマンさんがおっしゃられていた、神奈川県での取り組みなどをお聞きするに、アメリカを中心とした「多文化教育」の実践、アプローチなどは、有効な手がかりになるのではないかなと思います。

※【エスニシティ論】社会学や文化人類学などの分野で1960年代後半から使われるようになった、「多民族国家」のあり方や「多文化共生」の議論と深く関わる概論。
日本における「多文化教育」の課題
ここで日本での「多文化教育」が抱える課題について考えてみたいと思います。ご存知の通り、日本国憲法第26条には、義務教育(※)が定められています。これは、日本国籍を持つ保護者は自分の子どもに対して必要な教育を受けさせることが義務であるという条文で、子どもたちはその権利の享有主体である、とみなされています。従って外国籍の家庭の子どもたちに関しては、この条文の適用外であるという見方が依然としてあり、外国につながる子どもたちが義務教育を受けるのは、特別な許可のもとで行われる、といった解釈になっているのが現状です。
これに対して、一部の社会学、教育社会学者の人たちは、これだけ多くの外国につながる子どもたちがいるのだから、その子どもたちも義務教育の対象としたらどうかという主張をされています。しかし一方、日本のカリキュラムや指導要領は原則として日本国民の教育を前提としているので、外国につながりを持つ子どもたちを義務教育の対象と純粋に解釈して受け入れた場合、日本の教育の内容自体がその子どもたちを想定したものではなっていない、という矛盾が表面化してきます。
それから、これは「多文化教育」を考える際にとても興味深いことでもあるのですが、日本の教育のやり方と、海外の教育のやり方の違いについても理解しておく必要があります。私が多文化教育コーディネーターとして関わった神奈川県のある高等学校では、中国、フィリピン、南米、ネパール、ベトナムなどから来た子どもたちがおり、その子どもたちに、母国での学び方と日本での学び方の違いについてインタビューしたことがあります。その結果、多くの子どもたちが戸惑っているということがわかりました。何に戸惑っているかと言いますと、昨今の日本の高等学校の授業というのは、自由な発言を促したり、ディスカッションを行ったり、宿題にしても何かを自分で調べてきなさい、といったことが多く行われているのですが、こうした自発的なことを要求される授業に慣れていないということです。特に中国などでは、知識詰め込み型の教育が行われていて、子どもたちもそれに慣れています。 意外でもあったのですが、フィリピンやネパールの子どもたちも似たような反応でした。そうした国から来ている子どもたちにとっては、自由な発言をしなさい、といわれても言葉の問題と相まって、何を喋れば良いのかわからない、となってしまうわけです。
意外でもあったのですが、フィリピンやネパールの子どもたちも似たような反応でした。そうした国から来ている子どもたちにとっては、自由な発言をしなさい、といわれても言葉の問題と相まって、何を喋れば良いのかわからない、となってしまうわけです。
もうひとつ、私たちは「隠れたカリキュラム」と呼んでいるのですが、これに対する戸惑いというのもあります。これはつまり、その集団が持つ行動様式やメンタリティをどのように学び、母国のそれとの違いにどう折り合いを付けるか、ということですね。例えとして適切かどうかはともかく、母国では先生というのは非常に厳しくて、一定の距離があったのに、日本では生徒が先生を平気で呼びつけにしている、なんていう光景は、ある国々の人たちにとっては相当困惑してしまうわけです。それが日常であれば、「良い生徒」であることの基準ももうわからなくなってしまいます。
日本の場合、ひとり一人の考えにはさまざまな違いがあるはずなのですが、全体としてはよくも悪くも「一斉共同体主義」のような「振る舞い」を見せることが多く、そうした「モノカルチャリズム」、「モノリンガリズム」といったようなものが、かなり支配的になっています。こうした「振る舞い」こそが「隠れたカリキュラム」となって、どう消化したらいいのか、外国につながる子どもたちを悩ませる要因のひとつになっています。
これらの課題を見てみますと、日本の「多文化教育教育」の現状がわかってくると同時に、教育というのは、法律やしくみ、そしてその国の文化そのものと非常に強く関わるものであると認識せざるを得ません。教育そのもの自体が、そもそも多文化的な問題を孕んでいる領域なのではないかと思われます。

※【義務教育】日本国憲法第26条には、2つのことが書かれている。ひとつは全ての国民は、その能力に応じて等しく教育を受ける権利があること、もうひとつは全ての国民は、自分の子どもに普通教育を受けさせる義務を負っていることである。つまり子どもたち自身に義務がある訳ではなく、あくまで親の義務である。いずれの条文も「国民は…」となっていることから、外国人の子どもの初等・中等教育については、これに該当するか否かについてさまざまな解釈論にゆだねられているのが現状である。国際的には国連による「子どもの権利条約」によって、世界中の子どもは本来普遍的な教育を受ける権利があるとされる。
特別なものから普遍的なものへ。日本に課せられた課題
ここまで、「多文化教育」のルーツや日本での課題の数々について述べてきました。しかし、日本において「多文化教育」が疎かにされてきたかというと、必ずしもそうではなく、1970年代〜80年代にかけての同和教育や、オールドカマーといわれる在日コリアンの人たちへの教育施策は、ここで言う「多文化教育」に通じるものであったと考えられます。特にこの神奈川県や、大阪府ではこうした教育が進んでいました。
1990年代になると、今度はニューカマーと呼ばれる新しく海外からやってきた人たちの子どもへの教育的な取り組みがありました。例えば1992年には当時の文部省から、学校に5人以上の日本語指導が必要な子どもがいる場合には、対応する教員を一人加配する、といったような政策が打ち出されています。その後、変遷はありますが、2014年には日本語指導を受けた生徒に対して、それを教育課程として正式に認めるといった通達も出されるようになりました。このように日本語教育ということでは、歴史や実績もあるのですが、総合的な支援としての「多文化教育」の施策となると、まだまだ整備がされていないのが現状です。
そうしたなかで、私自身や、先ほどお話しいただいた中村ノーマンさんたちが神奈川県や川崎市などで外国につながる子どもたちへのさまざまな支援活動を行ってきたのですが、当初は自治体の方々に向けて外国につながりを持つ人と一般市民との多文化共生を訴える、という作業だけでも、けっこうな苦労がありました。自治体としては、どうしても国際化というと外資系の企業を呼び込むための施策などといったことのほうに関心がいきがちで、外国につながる人たちとともに文化を育てるといった考え方とはどうしても乖離があるわけですね。しかし、自治体側の施策のなかに、なんとか「多文化共生」や「多文化教育」の理念を持ち込んでいただき、徐々に進めて行く、といった方向付けはできつつあると思います。
ひとつの成果として、神奈川県立鶴見総合高等学校というところでは、2012年に「多文化共生教育指針」が策定されました。 この学校はいわゆる在県枠などがなかった1990年代から、外国につながる子どもたちの受け入れに積極的な学校で、日本語教育、母語の学習、教科学習、進路指導など、多岐にわたる支援をずっと行ってきたのですが、それを最近になって明文化したということに意義があったと思います。この指針づくりには私も関わったのですが、基本的な精神として、支援する側とされる側といった関係性を排除し、もともと対等な立場にあり、日本人の生徒も外国につながる人たちから積極的に学んで行くべきであるとしています。先生方の中にも、外国につながる子どもたちへの支援というのはなかなか大変で、負担になっていると思われるケースもあったようですが、明文化することによって、そういった基本的な精神も支援活動も含めて、学校にとって財産であり、全ての生徒の教育にもつながるといった視点を持つことができるのではないでしょうか。
この学校はいわゆる在県枠などがなかった1990年代から、外国につながる子どもたちの受け入れに積極的な学校で、日本語教育、母語の学習、教科学習、進路指導など、多岐にわたる支援をずっと行ってきたのですが、それを最近になって明文化したということに意義があったと思います。この指針づくりには私も関わったのですが、基本的な精神として、支援する側とされる側といった関係性を排除し、もともと対等な立場にあり、日本人の生徒も外国につながる人たちから積極的に学んで行くべきであるとしています。先生方の中にも、外国につながる子どもたちへの支援というのはなかなか大変で、負担になっていると思われるケースもあったようですが、明文化することによって、そういった基本的な精神も支援活動も含めて、学校にとって財産であり、全ての生徒の教育にもつながるといった視点を持つことができるのではないでしょうか。
このように、外国につながる子どもたちの支援を、特別なものから、普遍的なものとして認識していくことが非常に大切です。国際化がここまで進んできた現在、ここまで述べてきたような課題は日本社会の側が真剣に考えて行かなくてはならない重要な課題となるでしょう。日本にはいまだに血統主義的な考えが強いとはよくいいますが、日本人らしさや、日本的なもの、というのを揺るがすことなく、「多文化教育」や「共生社会」を語ることは充分にできるはずです。先ほど、教育とは、それ自体に多文化的な要素を含んでいると申し上げましたが、そうであればなおさら、あたりまえの議論として、これまでの社会が歴史的にどのように作られてきたのか、これからどうあるべきかといったことについて、私たちの関わっている神奈川県はもちろん、日本全国で活発な議論がされることを望みます。