【レポート】第1回メディカル&ケアテックパートナリングカンファレンス
2024.08.30


2024年8月1日、横浜市立大学サテライトキャンパスにて、「第1回横浜市立大学メディカル&ケアテック パートナリングカンファレンス〜医療支援スタッフ(看護師、薬剤師、臨床工学技士等)が医療現場の課題・ニーズを語る〜」を開催しました。
当日は会場、および、オンラインを含めて200名を超える方々にご参加いただき、横浜市立大学付属病院の看護師・薬剤師などの現場での課題やニーズを知っていただくと共に、参加企業のみなさまと課題の本質や解決のアイデアに関して対話を通じて新たな連携事業の創出や医療サービス・患者のQoL(Quality of Life)の向上を図りました。
当日は会場、および、オンラインを含めて200名を超える方々にご参加いただき、横浜市立大学付属病院の看護師・薬剤師などの現場での課題やニーズを知っていただくと共に、参加企業のみなさまと課題の本質や解決のアイデアに関して対話を通じて新たな連携事業の創出や医療サービス・患者のQoL(Quality of Life)の向上を図りました。
挨拶


横浜市立大学 附属病院 病院長 遠藤格
本日は多くの方々にご参加いただき、感謝いたします。
私たちは、イノベーション創出を推進して「研究の横浜市立大学」として取組を加速すべく、今年4月に共創イノベーションセンターを新設しました。私自身、過去にパートナリングでプロジェクトに取り組んで実感したのは情熱の大切さです。本カンファレンスを通じて医療現場での課題やニーズ、そして、医療従事者の情熱を感じていただき、パートナリングに活かしていただけると幸いです。


横浜市立大学 共創イノベーションセンター 副センター長 小林雄祐
今年4月に新設した共創イノベーションセンターは、産学官民の共創を推進することで学内外のシーズの事業化・社会実装を加速し、社会課題の解決・理想の未来社会の実現に貢献していくことを目指す組織として活動し始めました。
課題が明確であった20世紀の社会と異なり、現在は社会の単位毎に目的・課題の解像度を高め、ソリューションを共創して複雑な課題を解決していくことが求められています。このような新たなパラダイムシフトにおいて、私たちはアジェンダ(目的)からみなさんと一緒に対話しながら社会課題の解決、社会価値の共創を進めていきますので、ご協力・ご支援をお願いいたします。
事例紹介


薬剤部 山本幸二郎
「医療現場での薬剤師の課題〜現状と未来への展望〜」
病院薬剤師の業務は調剤業務、注射薬調製業務、持参薬鑑別業務、医薬品情報業務、医薬品管理業務など多岐にわたります。今後は対物業務の効率化を図り、対人業務(患者ケア)の充実を目指していますが、他職種へのタスクシフティングなどの課題があります。支援機器の充実、AIの活用などを通じた課題解決、そして、薬物療法に関わる患者のQoL向上に貢献していく所存です。


臨床検査部 矢島智志
「医療現場における予約管理の課題・ニーズと企業連携への期待」
臨床検査技師は検体検査と生理機能検査を担当しています。一日に扱う平均検体数は臨床検査部では一般300件、血液900件と多く、電子カルテに連動した予約システムはあるものの、一部手書きの手続きも残っており、完全デジタル化による他スタッフとのリアルタイム共有が課題となっています。
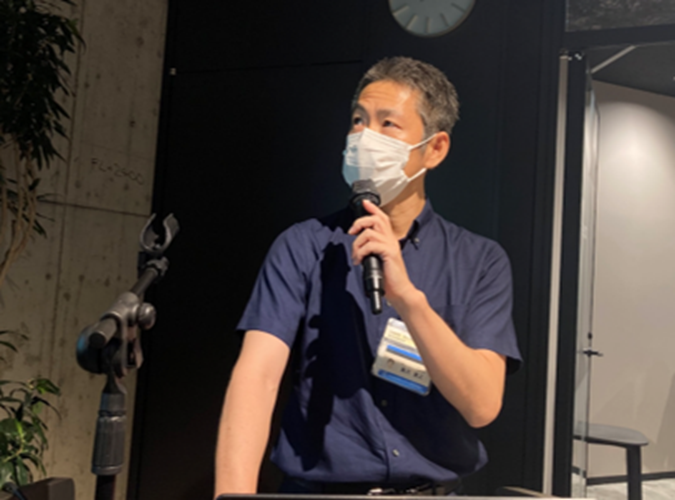
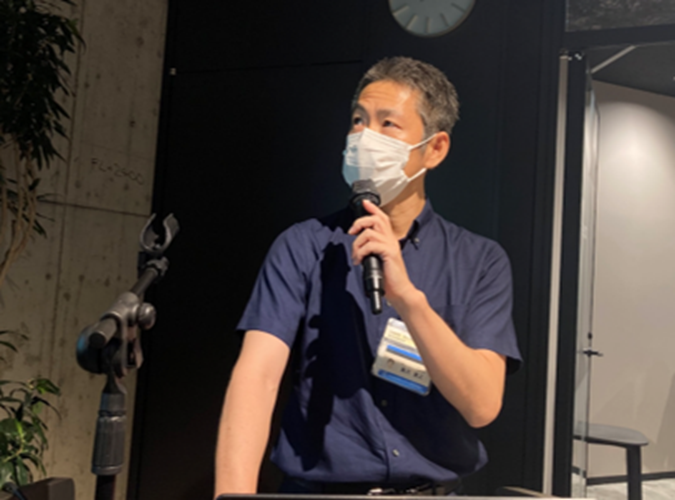
臨床検査部 黒沢貴之
「医療現場における身体的負担解消への期待」
採血は人によって様々な特徴があるので集中力と体力が必要になります。オランダでは自動採血ロボットが導入されていますが、血管の立体的な可視化やAIによる細胞識別システムなど、身体的負担解消の支援を期待しています。
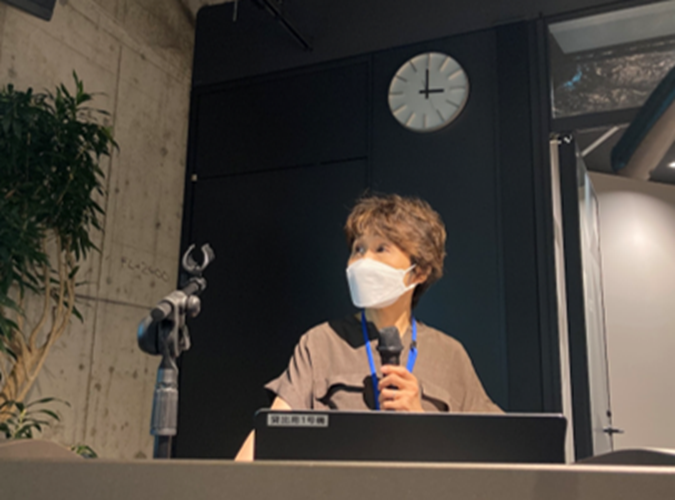
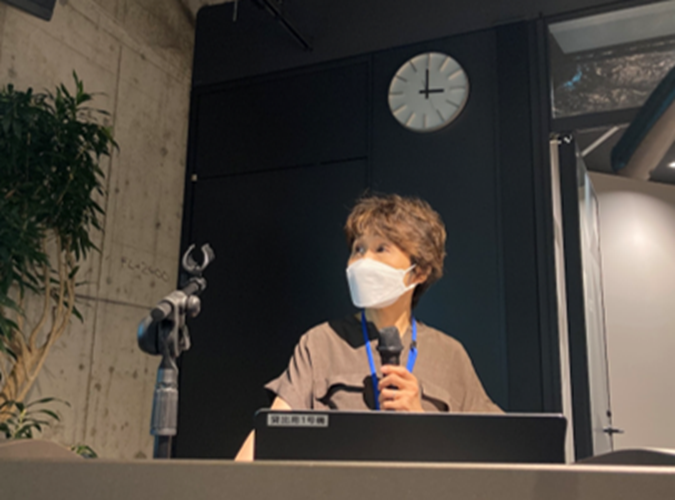
臨床検査部 原田佐保
「3本目の手が欲しい!手を使わずに声で操作する部門システム」
輸血が遅れると命に関わる時があるので1分でも早く使用場所に届ける必要があります。不適合がないように異型適合血の判定システムを利用していますが、バーコードリーダーとパソコンの操作や払出票に押印などの作業が多いため、キーボードでなく音声入力への代替による操作時間の短縮が望まれます。
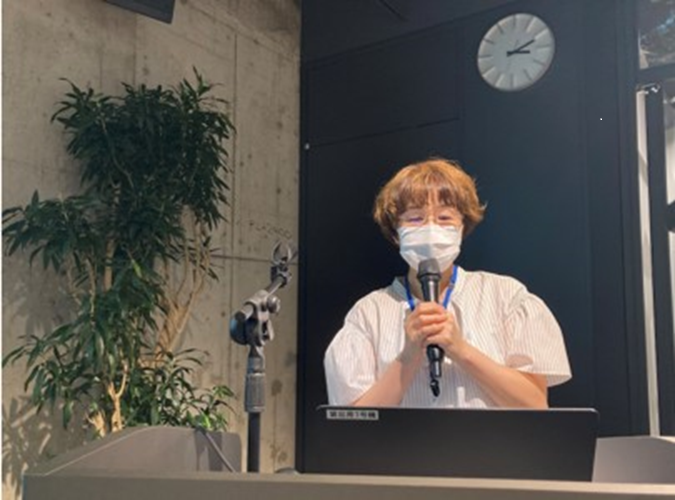
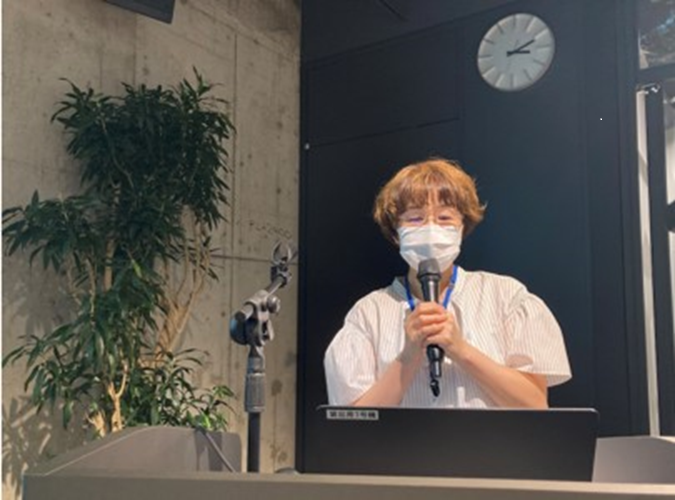
臨床検査部 西尾由紀子
「医療現場における検体紛失、検体管理の課題・ニーズと企業連携への期待」
病理業務では試薬として多種類の化学物質を使用し、中には危険で有害な化学物質も取り扱っています。細かな作業が多く、検体をカセットやパラフィンの入った包埋皿に移す際に紛失のリスクがあるため、ICチップ内蔵による検体紛失防止システムを期待しています。
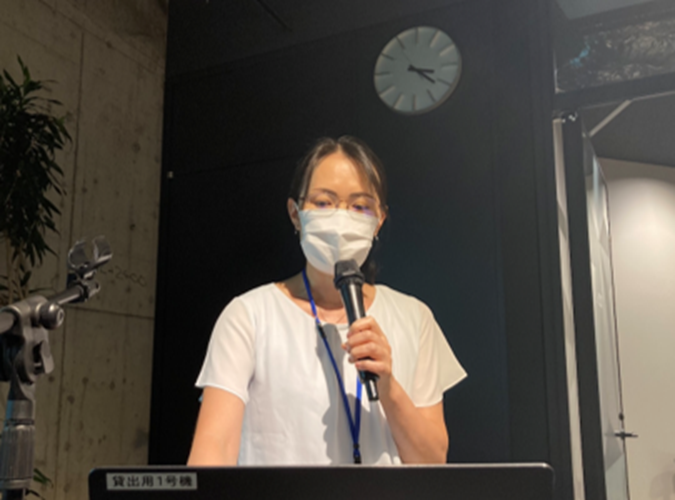
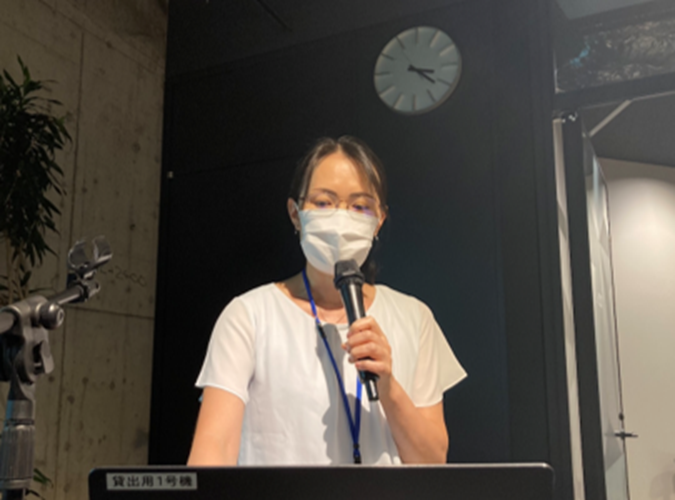
臨床工学センター 川上千年
「臨床工学技士の課題 ○○年後の未来を変えるために」
臨床工学技士は生命維持管理装置や人工呼吸器などのメンテナンスを担当し 、当病院では5,000台の機器を管理しています。医療機器にも使用期限があるため、他病院との連携などによって食品ロス削減同様に医療資材ロス削減に取り組みたいです。


臨床工学センター 鎌田文哉
「医療機器管理データを活用した保有機器の最適化」
医療機器は高額で一度購入したら終わりでなく、購入計画→購入→保守・点検→更新計画のライフサイクルの管理が必須です。機器の保有数が増えるとメンテナンス費の増大、保管場所の確保、保守人員の確保などの対策が必要となるため、医療機器管理データを活用して保有機器の最適化を図ることが望まれます。


看護部 看護部長 鈴木久美子
「我が国の医療現場における看護の現状と課題」
2024年4月から医師の時間外労働の上限規制がされ、看護職に求められる役割や業務が増大しています。持続可能な看護提供体制の構築に向けて看護職員の働き方改革が急務であり、夜勤交代制勤務の負担軽減、多様で柔軟な働き方などを推進し、限られた人材でも安心で安全な質の高い看護の提供を目指しています。
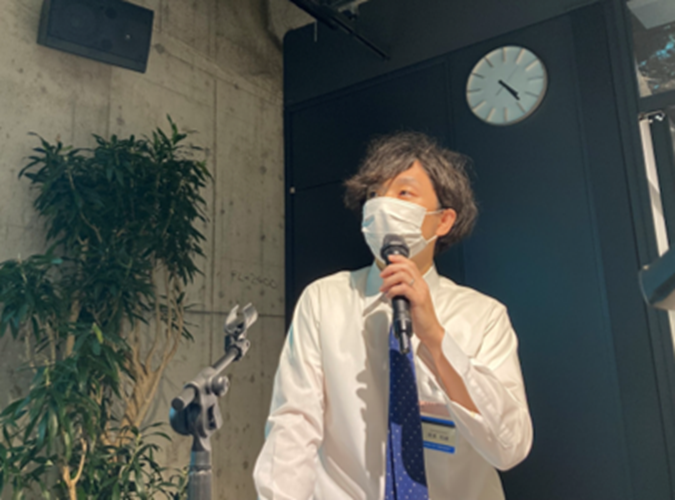
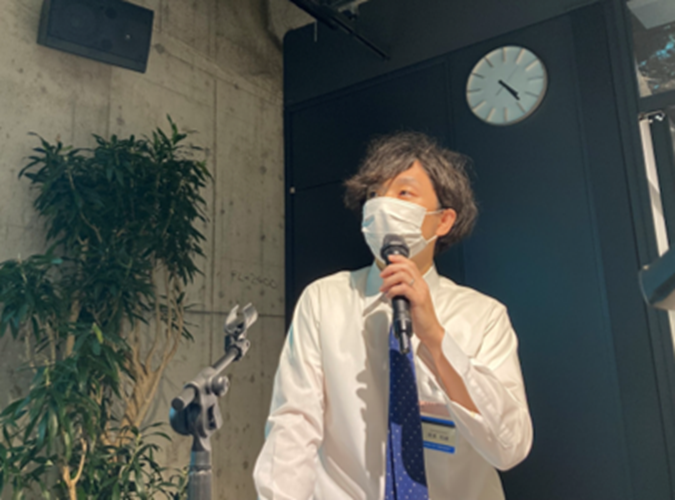
看護部 副看護師長 岡泉和樹
「快適な療養環境について」
ベッドの患者の体勢を整える際に複数人で対応する場合もあり、看護師の身体的負担も大きく50%以上の看護師が腰痛を患っています。介助者一人でも身体的負担を軽減して入院患者を介助できる機器の導入が望まれます。


看護部 看護師長 三浦友也
「看護の未来について〜寄り添う看護とDXのイノベーション〜」
この20年間で医療現場のDXが進み、例えば、患者確認の方法もダブルチェック・指差し呼称からスマートデバイスの利用に変化しました。今後、さらなるDXによるイノベーションとして、患者さんの動きを制限しない医療機器、行動制限しなくてもよい服・ベッド、転んでもケガしない服・床の開発・導入を期待します。


医学部 看護学科 教授 玉井奈緒
「看護×医学×企業で目指すケアイノベーション」
摂食嚥下のケアでは誤嚥性肺炎予防と安全な食事摂取のために誤嚥・残留を簡単かつ正確に判断できるシステムと共にエコーで判別しやすい摂食・嚥下ゼリーの開発が望まれ、実現することで患者さんに食べる喜びを取り戻したいと考えています。
横浜市立大学発認定ベンチャー企業「株式会社CROSS SYNC」


株式会社CROSS SYNC 三田杏祐様
「医療の今を変える。」
「ICU Anywhere」をビジョンに掲げて、あらゆる病床にICU並の医療を提供することを目指しています。弊社が開発・提供する生体看視アプリケーション「iBSEN DX」によってベッドサイドから離れた場所でも複数患者の様子をモニタリングできます。遠隔ICU導入を通じて医療従事者不足への対処、働き方改革、医療の質の標準化、安全管理の担保、医療コストの削減の貢献に努めています。
今回のカンファレンスは、医療現場の課題やニーズをきっかけに参加企業のみなさんとの対話を通じてイノベーションが生まれる期待を感じさせる場となりました。今後も共創イノベーションセンターは一人ひとり輝くウェルビーイングを共に叶えるために対話・共創を推進していきます。


